前回まで、DeSeCoが示したこれからの教育の目標であるキーコンピテンシーをみてきた。いわば、教育はこれから何処に行けばいいのか(where)という点をふれたが、今回は、行き先が見えてきたならば、そこにどうやって行けばいいのか(how)という点をみていきたい。
キーコンピテンシーのポイント
繰り返しになるが、まず行き先であるキーコンピテンシーについて簡単に確認したい。
DeSeCoによると、現代の社会は、次のとおり「変化」「複雑」「相互依存」という特徴を深めているという。
- 技術は急速かつ継続的に変化している。したがって、技術を扱う学習には、一連の作業を一時的に身につけることだけではなく、適応しつづける能力が必要となる。
- 社会はより多様化し細分化している。したがって、個人的な関係において、自分と異なる者と交流することがより必要となっている。
- グローバリゼーションは新しい形の相互依存を作りだしている。したがって、活動は、地域や国のコミュニティを超えて大きく広がる影響(例えば経済競争)と結果(例えば公害)に左右される。
このような特徴をもつ現代において、人と社会が豊かになるためには何が必要か。この問いを6年間かけて研究したDeSeCoは、次のようなキーコンピテンシーを創った。
ポイントは、態度、感情、倫理、モチベーションなどの「非認知的要素」の開発がなければキーコンピテンシーを身につけることができない、言い換えると、非認知的要素の開発をこれからの教育の目標として設定した、という点にある(知育中心の教育から徳育中心の教育への転換)。
※詳細は第30回 これからの教育からみた柔道(2) – 勇者出処 ~嘉納治五郎の柔道と教育~を参照。
認知的技能と知識は、明らかに伝統的な学校プログラムを通じて達成される重要な学習成果であるが、コンピテンシーに関する考察はそうした認知的要素だけに限定することはできない。
労働市場での行動や知性と学習に関する最近の研究は、態度や動機づけ、価値といった非認知的要素の重要性を示している。これらの要素は、フォーマルな教育の領域では必ずしもあるいは全く獲得されず開発されていない。
(キーコンピテンシー27頁)。
識者の意見
このキーコンピテンシーは従来の教育を大きく変更するものであるが、例えば、教育学者の福田誠治氏は、明治維新に生じた教育目標の大転換に匹敵するとして次のようにいう。
ちょうど、幕末から明治にかけて、日本は諸藩から国家に再編成される時に、一人前の能力観から学校で身につける能力観に変わった。
今、諸国から広域連合にあるいは地球規模に経済や政治が再編成される時に、学校で身につける学力観は固定的な学力取得ではなく、生涯学習として開発し続ける能力観に変わりつつある。日本はそれに対応した国家戦略をもっているのか。
教育再生会議などを通じて持ち出される対策は、「愛国心」や「学力テスト」のような訓練的学力観であって、「攘夷!」「攘夷!」と叫んで鎖国を続け、武術の鍛錬に励もうとする斜陽の武士に似ていはしないか。
今の日本に、国内でしか通用しない知識や偏差値や学力テストの順位を過大視する大人の何と多いこことか。子どもたちの生きていく世界は、それとは違う明日の世界なのだ。私たちは「未来の学力」を子どもたちに用意しなくてはならない。
(福田誠治「フィンランドは教師の育て方がすごい」226頁)
また、教育学者の門脇厚司氏は「このようなOECDの認識と決定に照らして日本の教育の実際をみてみると、落差の大きさに唖然とし憮然とする。」として次のようにいう。
もっと分かりやすく言えば、OECDは学校教育の目標を、「次の時代の社会の担い手としてふさわしい人間に育てること」にしたということである。教育目標を、人類社会が遭遇することになるであろう様々な難問を、自分の力で、あるいは他の人と力を合わせて、解決し乗り切っていける能力を備えた人間として育てることに定めたということである。
このようなOECDの認識と決定に照らして日本の教育の実際をみてみると、落差の大きさに唖然とし憮然とする。
小学校の教育は、よりいい中学校に入学するための点取り競争に、中学校の教育はよりいい高校に入るための点取り競争に、そして、高校の教育もまたよりいい大学に入るための点取り競争になってしまっているからである。これが日本の教育の実際であるのに、あろうことか、文部科学省は学力の向上を御旗に全国学力テストを開始し、こうした競争をいっそう加熱するというありさまなのである。
このような教育が行われている日本において、教師や親たちの頭から、児童・生徒・あるいはわが子が、最終的には、「社会人になる」という意識がすっかり抜け落ちてしまうのは当然のことである。こうしたありさまがこれからも続いていくとしたら、他者と協力しながら社会の問題を解決していこうとする態度やそれができる能力など身につくはずはない。そうなった時、日本の10年後、20年後はどうなるのか。社会の弛緩や破綻があちこちで顕在化するのが眼に見えている。
(門脇厚司「社会力を育てる」167頁)
現在の教育の問題点
DeSeCoも上記の識者も、テスト勉強のための教育に終始し、非認知的要素の開発を阻害する現代の教育を批判しているが、もうすこし具体的にいうと、何が一体問題なのだろうか。
この点、教育学者の佐伯胖氏は次のように指摘する。
教育の問題を本気で考えるとすると、コトはもっと複雑で深刻である。端的に言えば、子どもにとって、「わかること」や「できること」の意義が見えなくなってきている、ということである。「わかって、何になる」、「できたからといって、それがどうした」ということである。
こういう「わかって、何になる」式の不安と「先の見えない」閉塞性が、教室全体にかぶさり、教師や子どもも、それに圧し潰されていることがありありと観察できる。そこで子どもはやる気を失うか、受験という目の前の目標に自らを縛り付けて、「それ以外は考えないことにする」ということで当座を切り抜けようとしている。
教師も同じであって、教材をどういじっても、教授技術をどう工夫しても、「先がない」状態での一時しのぎをしているのではないかという疑問と不安をぬぐい去ることはできない。そこでともかく日々、カリキュラムにしたがって、「これを教えるのだ」と自らを限定してカラ元気で動き回り、気をまぎらせているのが現状である。
(「状況に埋め込まれた学習」解説184~185頁)
「わかって、何になる」「できたからといって、それがどうした」。
学ぶことの意義が見えないのである。
これを社会人に置き換えるならば、「自分の仕事は誰の役に立っているのだろうか。」と疑念を感じながら、自分を押し殺して働くという状態だろう。
一方のバケツから他方のバケツに水を注ぎ、次にそのバケツから元のバケツに水を戻す、このような意味の無い作業を延々と強いられた囚人は自殺してしまうと話があるが(ドストエフスキー「死の家の記録」)、学ぶ意義を感じないにもかかわらず学びを強いられた場合、人はどのような影響を受けるのだろうか。
少なくても、非認知的要素が発達した人間、「革新的、創造的、自律的、自発的」な人間に成長することが難しいことは明らかだろう。
非認知的要素を開発する方法
それではどうしたらいいか。
認知的要素と非認知的要素がともに開発できる教育、キーコンピテンシーを身につく教育の方法とはどのようなものなのか。
例えば、嘉納がとった主な方法は、徳育としての体育の振興や優れた教師の育成である。
柔道の創始普及や日本のオリンピックの参加など、あらゆる手段を尽くして嘉納は徳育としての体育の振興に努めた。
※詳細は第31回 これからの教育からみた柔道(3) – 勇者出処 ~嘉納治五郎の柔道と教育~を参照。
また、子供と大人の交流する機会を増やすこと(第33回 これからの教育からみた柔道(5) – 勇者出処 ~嘉納治五郎の柔道と教育~)、幼少期に倫理的な読書経験を積むこと(http://d.hatena.ne.jp/sakais/20110515:title=http://:title]も必要である。
様々な方法があるが、今回は「そもそも「学習」とは一体何なのか?」と問い、「学習」という概念や営みそのものを根本的に捉え直すことによって、これからの教育のあり方を示したレイブ氏とウエンカー氏の状況的学習論(著書「状況に埋め込まれた学習」における「正統的周辺参加」(LLP))をみていきたい。
現代の「学習」概念の問題点
それでは「学習」の概念について何が問題か。
DeSeCoも状況的学習論を参考にしているが、このDeSeCoは現在の「学習」概念について次のように批判する。
DeSeCoで見出された能力の概念は、政策にとって重要な意味を含んでおり、伝統的な教育と学習の方法の妥当性と有効性について疑問を引き起こす。
・・全人のためのコンピテンシーとキー・コンピテンシーを育成し、強化しようとする場所としての学校(教授と学習に責任がある近代社会の初等教育機関)の意味は何か?
学校は訓練の基礎的カリキュラムを通して、知識や認知スキルの伝達を伝統的に強調してきた。
・・ゴンチ・・は、まるで心が容器であるかのように事実、知識、信念、および観念で学習者の心を満タンにしてしまう、この伝統的な学習の概念に対して強く疑問を投げかけている。
「古い学習理論のパラダイムは、学習が生じる環境に学習者を結びつける新しいパラダイムに代えられる必要がある。新しい学習の概念は、個人の認知的側面と同様に、感情、道徳、身体を考慮したものであり、そして現実の学習が行為の中で、および行為を通してのみ生じるという。したがって、キー・コンピテンシーの学習は、判断を下す力量をおそらく生涯にわたって増大させるという点で、現実の世界への働きかけを通じてのみ生じることができる・・。」
つまり、DeSeCoは、以下のようなことを言っている。
- 現在の「学習」という概念は、学ぶ人を「空っぽの容器」と捉え、知識や技能を「空っぽの容器」に注ぎ込むものというように理解されている。
- しかし、学ぶ人は、感情があり、身体があり、アイデンティティがある生身の人間であって、「空っぽの容器」ではない。
- この点を無視し、「空っぽの容器」であるという前提のもと無理に知識や技能を注ぎ込むことから、キーコンピテンシシーの重要な要素である「非認知的要素」の開発が損なわれる。
- つまり、現代の教育はキーコンピテンシーの育成方法として適当ではない。
- したがって、「空っぽの容器」に知識や技能を注ぎ込む、という現在の学習概念を捉え直し、新しい学習概念を創らなければならない。
新しい「学習」概念
それでは、レイブ氏らの状況的学習論における新しい「学習」の概念とはどのようなものだろうか。
結論から先にいうと、状況的学習論では、「学習」とは「空っぽの容器に知識や技能を注ぎ込むこと」ではなく、「共同体に参加すること」であり、「参加のプロセスを通じてアイデンティティを創りあげること」であると捉える。
現在の「学習」の概念とは大きく異なるが、以下みていきたい。
ポイントは「仕事での学びと学校での学びは全然違う。」という大抵の社会人が有する感覚のなかにある。
例えば、次のような二つの例があるとする。
ある会社の社員が、上司から「今日からロシアを担当してもらう。よろしく。」といわれ、ロシア語をゼロから勉強することになった。「何故、俺がロシア担当なんだ。」とは思ったが、仕事を続けるうち、半年後、彼はロシア語をそれなりにできるようになった。
他方、ある高校では二年生はロシア語が必修となっている。高校生は「何故、英語ではなく、ロシア語を勉強しなきゃいけないんだ。」と思いながら勉強をし、半年経ってもあまり上達しなかった。
仮にこのような事例を考えた場合、ロシア語の上達の程度に差が出た理由はどこにあるだろうか。
大半の人は上達に差が出て当然だと思うだろう。「仕事の学びと学校の学びは全然違う。」と。
では、この自明なことをもう少しつっこんで考えてみると何が違うだろうか。
仕事は、上司や同僚、部下、お客さん、取引先など様々な関係者と関わりながら、誰かの何かの役に立つことをするプロセスである。この役に立つことをする過程でロシア語の学習が必要となり、結果的にロシア語の勉強をすることになる。
つまり、会社員の事例では、高校生の事例と異なり、ロシア語の習得がそれ自体が独立した目標ではない。あくまで誰かの役にたつことをするという中で結果的に必要とされるものである。
このようにロシア語を学ばなければ仕事が出来ないという状況にあれば、単に勉強する又はテストや進学のために勉強する場合と比較して、学習効率が大きく異なることは誰しもが体感している。
さて、ここからがポイントであるが、仕事をする過程で結果的にロシア語を勉強するという営みは、さらにつっこんで観察してみると、一体何を意味しているだろうか。
状況的学習論は、まず、「新参者」が「共同体」へ「参加」するプロセスであると捉える。
例えば、会社の新入社員や新しい部署に配転した社員は、仕事をするために必要なことを学ばなければならないが、学んで仕事ができるようになれば、上司や同僚、部下や取引先などを関係性を持つことができる。学ばずに仕事が出来なければ関係性を持つことが出来ない。「学習」とは、会社という「共同体」に「参加」するプロセスなのである。
その上で、状況的学習論は、「学習」とはアイデンティティが形成する営みであるという。
つまり、仕事ができるようになると、「新参者」が次第に「熟練者」になり、共同体の中での位置が周辺から中心に移動していくが、このプロセスの中でアイデンティティが変容していく。
例えば、新入社員が、仕事を覚えて経験を積み重ねるにつれて、頼もしい人になっていく。部活動の新入部員が稽古を重ねるにつれて次第に逞しい人になっていく。
これは共同体の周辺にいた「新参者」が次第に「熟練者」として中心に移行する過程で、アイデンティティが変容していくと捉えるのである。
・共同体と学習者にとっての参加の価値のもっと深い意味は、共同体の一部になるということにある。したがって帽子をかなりうまく作ったということは、仕立て人の徒弟が「一人前の職人」になったということの証拠なのである・・・十全的参加に向けての移動は、より多くの時間をさくこと、労力をより一層注ぐこと、共同体内でより大きな、より広い責任をもつこと、より困難な、危険を伴う作業につくこと、などだけではない。もっと重要なことは、熟練した実践者としてのアイデンティティの実感が増大していくということである。(「状況に埋め込まれた学習」97頁)
私たちは、アイデンティティの発達は新参者の実践共同体の経歴の中心であり、したがってそれが正統的周辺参加の概念の基礎であるということを主張してきた。・・実際、私たちは本書で展開した観点から、学習とアイデンティティ感覚とが分離し難いものであると論じてきた。両者は同一の現象の異なる側面なのである。(「状況に埋め込まれた学習」103頁)
非認知的要素の開発プロセスの「見える化」
では、このように「学習」の概念を根本的に捉え直すことによって一体何が可能になったか。
従来の「学習」の概念は、学習者を「知識や技能を注入される空っぽの容器」と捉えたが、モチベーションや態度、感情、倫理といった非認知的要素については「空っぽに容器に注ぎ込んだ」としても身につくものではない。つまり、非認知的要素の開発は想定外だった。
したがって、先の高校生の事例でいうと「空っぽの容器にロシア語を注ぎ込んだ」結果、「ロシア語ができて何になる」「できたからといって、それがどうした」ということになる。ロシア語ができたときのメリットを「注ぎ込んでも」やる気がでるわけではない。
しかし、状況的学習論は、学習者を「共同体への参加のプロセスを通じてアイデンティティを構築する主体」として捉える。つまり、共同体の周辺から中心に移行する過程において「アイデンティティ」が形成される、すなわち非認知的要素が開発されると捉える。
先の会社員の事例で、「なぜ自分がロシア関係の仕事をしなければならないのか。」という疑問は生じても、「なぜロシア語の勉強をしなければいけないのか。」という疑問は生じない。仕事をする、すなわち「共同体」に「参加」するプロセスでロシア語の勉強が必要であることは自明であるからである。
そして、仕事を積み重ね、周りの人々から「よくがんばった」「ありがとう」などというやり取りが行われる過程で、共同体の周辺にいた「新参者」が中心に移動しはじめ、次第に「自分はロシア関係の仕事ができる人」というアイデンティティを形成していく。
このようなアイデンティティの形成されると(=非認知的要素が開発されると)、ロシア語をさらに積極的に学ぶことになる。
いささか単純な例ではあるが、状況的学習論は、従来ブラックボックスであった非認知的要素の開発プロセスを「見える化」したのである。
この結果、状況的学習論は、非認知的要素を開発することができる「学習」には、「共同体」と「参加」が必要であることを明らかにした。
したがって、もしキーコンピテンシーを体得できる教育を目指すのであれば、「学校」の役割は大きく転換する。
「空っぽの容器に知識を注ぎ込むこと」から、「共同体」への「参加」をサポートすることに転換しなければならない。この点、佐伯胖氏は次のようにいう。
LLP(引用者注:正統的周辺参加の略。本稿では状況的学習論のこと)では学習をコントロールするのは実践へのアクセスであるとする。つまり、教材や教師の役割がそこにあるとすれば、学習者をいかにホンモノの、円熟した実践の本場(アリーナ)を当初からかいま見させて、そこへ「行ける」実感をもたせ、また、たとえごくごく周辺的であっても、そこにつながっているということがなんとなくわかるような、実践の手だてを講じてあげる、ということになる。
教師がやらせるから学ぶのではない。教師がホンモノの世界(円熟した実践の場)をかいま見させ、そこへの参加の軌道(trajectories)を構造化する一方、子どもはその世界との漸進的交流で、自ら学んでいくときの「共同参加者」となる、ということになろう。
(「状況に埋め込まれた学習」佐伯胖氏の解説190頁)
これからの柔道への視座
それでは、状況的学習論は、これからの柔道にどのような視座を与えるだろうか。
まず、状況的学習論は、柔道修行者が「精力善用」「自他共栄」という「道」をどのようにして体得するかという点に関し、新しい視座を与えてくれる。
つまり、「精力善用」「自他共栄」とはそれを体得した人から「教えてもらう」というものではない。同様に山に一人篭って修行すれば身につくものでもない。
「精力善用」「自他共栄」を主要な価値観としている「共同体」があって、その共同体に「参加」するプロセスにおいて体得するものなのである。
例えば、「親に無理やり道場につれられてきた素行不良の子どもが、稽古をするうちに素行が良くなった」というケース(第33回参照)は、柔道クラブという「共同体」への「参加」の過程で、すなわち、柔道が上達し、柔道クラブの中での位置づけが「新参者」から「熟練者」に移行する過程で、共同体が有している倫理や価値観(例えば、「礼節を守る」「努力する」「仲間を大切にする」「強い者は弱い者を助ける」など)を取り入れて、アイデンティティが変容したと捉えることができる。
逆に言えば、極端な話、勝者が敗者を蔑むのは当然であるということを主要な価値観とするクラブに参加したならば、技術の向上に同時に、人を蔑む人間に変容していく。
したがって、「精力善用」「自他共栄」を体得した人間を育成し、人類の共栄を図るという柔道の長期的目標を達成する方法とは、如何にして「自他共栄」「精力善用」を主要な価値観とする「共同体」をつくりだし、如何にしてそこにより多くの人の「参加」を促していくか、という問題に還元される。
まさに佐伯胖氏がいうように、「私たちははじめて、今日の教育をとりまく社会的・文化的問題と、一人ひとりの学習者の「学び」の問題を結びつける基礎的なフレームを得た」のであり、
「これを今後どのように展開していくかは、・・新しい協力関係をもった共同体をつくりだし、そこへの正統的周辺参加を、今から、みんなで、始めていくしかない・・」のではないだろうか(「状況に埋め込まれた学習」佐伯胖氏の解説190頁)。
新しい協力関係をもった共同体を作り出す方法
それでは、如何にして「自他共栄」「精力善用」を主要な価値観とする「共同体」をつくりだし、如何にしてそこにより多くの人の「参加」を促していくのか。
本稿の解は、既に何度も述べている通り、異なる地にある道場(国外・国内問わず)にいって、その地の先生の指導を受け、その地の仲間たちとともに稽古をし、その地でホームステイをさせていただき一定期間生活する、このような経験を万人に提供する仕組みを創りあげることである。
すなわち、「場」(プラットフォーム)を創り、ある道場で稽古をする青少年と、異なる地にある道場を結びつけ、単独では出せない価値を生み出すというものであり、世界各地の道場が手を取り合って、修行者を育成する仕組みである。
詳細は第27回 新しい仕組み内容と可能性 – 勇者出処 ~嘉納治五郎の柔道と教育~を参照。
異国の道場に参加した「新参者」は、柔道の稽古をともに行うことを通じて、次第に「共同体」の中心に移動し始める。この「異質な集団の中で交流」するプロセスを通じて、これからのグローバルな世界を生きるために必要なアイデンティティが構築されていく。
嘉納は、柔道について、特殊な好みをもった人向けのスポーツとしてではなく、「一般的に人間として必要な修養の方法と認められる」のであれば大きく普及するという。
かくして柔道が技術ばかりでなく、一般的に人間として必要な修養の方法と認められるようになれば、今日のようにある年齢であっても特にそういうことに趣味をもっているものばかりではなく、今いっそう一般的に行われるようになるに相違ない。遂には特殊の人の柔道でなく国民の柔道となることが出来よう。(嘉納・著作集2巻275頁)
柔道の技術は大切である。また貴重なものである。しかし、もし技術が単独に存在して智徳の修養に伴われていなかったならば、世人は左程柔道家を重んじないであろう。他の修養と離れた技術は、軽業師の技術と比較し得るものであって、特に取り立てて尊重する価値が認められまいと思う。柔道の修行者が文武の両道にわたって研究練習を積んでこそはじめて国家社会に大いに貢献することも出来、世人から尊敬を受くることも出来るのである。(嘉納・著作集第2巻89頁)
異国の地で稽古し生活をするという教育方法を取り入れた柔道は、これからの世界において「一般的に人間として必要な修養の方法」として認められのではないだろうか。
以上、全7回にわたって教育という視点からこれからの柔道をみてきたが、次回は日本という視点からみていきたい。
※本記事は、2010年8月から酒井重義(judo3.0)によってブログで連載された研究論考「勇者出処~嘉納治五郎の柔道と教育」の再掲です。

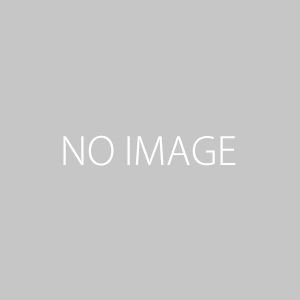
最近のコメント