今回は「異質な集団の中で交流すること(interact in heterogeneous groups)」をみていきたい。
内容
内容は次のとおりである。
- 他人といい関係を築く
- 共感:相手の立場にたって、その視点から状況を想像すること。これは内省を促すものであり、このとき、個人は、様々な意見や信念を熟考しながら、その状況で当たり前だと思っていたものが必ずしも相手と共有できるものではないことに気づく。
- 感情の効果的なコントロール:自分を認識している状態を保ち、自分自身と相手の心の底にある感情やモチベーションの状態を効果的に読み取ること
- 協力する。チームで働く。
- 自分のアイデアを出し、他の人のアイデアを傾聴する力
- 議論の流れを理解し、計画に従うこと
- 戦略的又は持続可能な協力関係を作る力
- 交渉する力
- 異なる様々な意見を考慮して決定をするキャパシティー
- 争いを処理し、解決する
- 異なる立場が存在しうることを認識し、問題となっている争点や利害(例えば、権力、メリットの把握、役割分担、公正さ)、争いの原因、あらゆる側面の論拠を分析すること、
- 合意できる領域とできない領域を確認する
- 問題を再構成する
- 進んで妥協できる部分とその条件を決めながら、要求と目標の優先順位をつける
意義
DeSeCoは、何故、「異質な集団で交流すること」が必要かについて次のようにいう。
人は、物質的にも精神的にも生きていくために、そして社会的なアイデンティティという点でも、人生を通じて、他の人々とのつながりに依存している。社会が様々な点でより断片化し、またより多様化するなか、個人の利益を得るという点でも協力関係の新しい形を作り上げる上でも、個人の人間関係をマネージメントすることは重要になっている。
既存の社会的つながりが弱くなり、新しい社会的つながりが強いネットワークを創る力をもった人々によって作られるように、ソーシャルキャピタルを創りあげることは重要である。様々なグループにおける、ソーシャルキャピタルを創り上げそこから利得を得る力の違いは、将来、不公平さの潜在的な原因の一つになる可能性がある。
このカテゴリーにおけるキーコンピテンシーは、他者と共に学び、生活し、働くことを個人に求める。このキーコンピテンシーは、「社会的能力」「ソーシャルスキル」「社会的スキル」「異文化間能力」「ソフトスキル」といった用語に関係する特性の多くに対応している。key competencies
参考:ソーシャルキャピタルソーシャル・キャピタル – Wikipedia
ポイント
それでは、このコンピテンシーのポイントを2点ほどみていきたい。
「異質な」
異質な集団(heterogeneous groups)の対義語は「同質な集団(homogeneous groups)」であるが、
第一のポイントは、これまでの人は「同質の集団」で交流すれば事足りたが、これから人は「異質な集団」で交流することができないと豊かな生活や社会を築くことはできない、ということが示した点である。
原語はheterogeneousとなっているが、このことばはhomogeneousと対をなす用語である。同質集団内では、コミュニケーションをして意見調整することはまず必要ない。それとは逆に、異質集団では、同一の行動を一斉に行うという集団行動が前提となっているわけではないので、諸個人あるいは諸団体の意見調整が必要となり、読解力という言語力が生きてくることになる。2(異質な集団で交流する:筆者注)の前提となっているのは、同質性ではなく異質性なのである。
(福田誠治「フィンランドは教師の育て方がすごい」212頁)
では、何故「同質集団」ではなく、「異質な集団」で交流することが求められるようになったのか。
この点、統合を進めるEUの例が分かりやすい。教育学者の福田誠治氏は、「異質なものを交流させる能力こそ、統合ヨーロッパにとっては死活問題となる」と指摘し、その理由を次のようにいう。
国民教育制度として、誰もが到達すべき国定の知識・技術を決め、正しい答えに向けて教え込むという教育は終わりを告げる時代に来ている。
国民国家を前提とした教育は、その目的を国民作りにおく。国民パックとも言うべき「知能・技能の国民標準」が定められ、同一の行動規範、同一の能力・知識・技能・意識が求められる。知識や意識が同一であるから、国民内での交流は不要であり、注入とプロパガンダ(宣伝ないし啓蒙)があればよい。教育とは正しい答えを教える啓蒙のことでしかない。
ところが現在のヨーロッパは、文化の蓄積と歴史のある国民国家を超越するEUを形成しなければならない。教育の統治を国家を超える機関に置き直すとともに、国民作りという教育目的を市民育成に置き換えざるを得なくなる。そうなると、行動規範は多元的となり、能力や知識や技能は異質なものが共存することを認めざるを得なくなる。だから、異質なものを交流させる能力こそ、統合ヨーロッパにとっては死活問題となる。
ここに、「国際教育指標(INES)事業」の活動主体としてのOECDが登場し、国際学力調査PISAに「読解力」を主要学力として組み込み、また、非認知的側面を重視する学力観を構成する要因が生じることになるのである。(福田誠治「フィンランドは教師の育て方がすごい」192頁)
政治的な統合を進めるEUは最先端の例ではあるが、貿易のグローバル化や科学技術の普及により「相互依存」はますます進み、同質集団の中で完結することはできなくなった。例えば、雇用の場をみても、外資系企業はもとより、海外展開する日本企業が外国人を雇用する割合は年々上昇し、また最近、楽天やユニクロ(ファーストリテーリング)は社内の公用語を英語にした。
要は、「義務教育(強制教育)」によって、「同一の行動規範、同一の能力・知識・技能・意識」をもった「国民国家」という「同質の集団」を作り、主に同質集団の中だけでコミュニケーションをし、異質な集団とのコミュニケーションは一部の限られた人だけが行って、発展するというパターンがうまくいかなくなった、ということである。
そこで、DeSeCoは、これまでの同質性を前提としたコミュニケーション能力の育成から、異質性を前提としたコミュニケーション能力の育成に、教育目標を転換すべきと提言した。
同質性を前提とした教育から異質性を前提とした教育へ
さて、これは、同質性を前提とした教育から、異質性を前提とした教育に転換するであるが、これが意味することは、「人間を全体集団として扱い、みんなが国民として同じ能力を身につけるべき」という教育観から「人間個々人が市民としてそれぞれ違う能力を身につけてよいと考える」教育観へ転換することである。
この点、フィンランドは異質性を前提とした教育の成功例といえるが、このフィンランドの教育を研究した福田誠治氏は、この教育における「コペルニクス的転回」について次のようにいう。
□
筆者は四年間に八度のフィンランド通いをしたのだが、日本とフィンランドの違いは、なかなか理解できなかった。なぜなら、まったく違う論理で日本の教育学が組み立てられているからである。
私たちは、子どもは一人ひとりみな違うという。その点では、日本もフィンランドも考えの違いはない。その一人ひとりに違った子どもが集まるので、クラスもまた一つひとつみな違う。この点でも、異論はなかった。すると、クラスが違えば、教師は違う対応をするでしょう。このようにフィンランドの教育関係者も行政官も言った。筆者は、クラスが違っても日本中同じことを教えていると言った。
日本の教師は、クラスのみんなに同じことを教え、クラスのみんなが同じことを学び、同じ学力をもつべきだと思っている。「どの子にも100点を」という発想は、その実、教師の想定する学力を持たない者は「落ちこぼれ」「できそこない」だと見なしていることになる。
一人ひとりが違っていて、その一人ひとりにかけがえのない価値があり、その一人ひとりが力を伸ばす努力を支援する、これがフィンランドの教育学なのである。ヒトは人間になろうと一人ひとりが同じように努力するけれど、結果は同じではない。違った能力が伸びていってもよいと考えるわけである。
日本からも、フィンランドの教師育成を探りに研究者がたくさん詰めかけた。だが、この教育学の相違に気づいた者は何人いるだろうか。(福田誠治「フィンランドは教師の育て方がすごい」48頁)
□
日本とフィンランドとの違いはどこから生まれるのか。
それは、人間を全体集団として扱い、みんなが国民として同じ能力を身につけるべきだと考えるか、人間個々人が市民としてそれぞれ違う能力を身につけてよいと考えるかという教育観の根本に発生する。それもフィンランドでは、学者だけでなく、行政官も、親も教師も生徒も、財界人も政治家も、たいていの人はそう思っている。
実は教育のコペルニクス的転回はここにある。
教える行為と学ぶ行為は授業で一体化すべきはずのものであるが、フィンランドは教える行為から学ぶ行為へと教育の重心を移しつつある。そして、グローバリズムに対応して、「知識・技能の国民パック」の伝達・注入を止めたのである。(福田誠治「フィンランドは教師の育て方がすごい」233頁)
□
筆者は、フィンランドでは「16歳までテストをしない」という点にこだわった。なぜテストがないのに子どもたちは勉強するのだろうか。これは、どう考えてもわれわれ日本人には理解できないことである。突き詰めて考えていくと、知識や技能は人それぞれ異なっていてよいという教育哲学と、それならば一人ひとりに合わせて支援するよう教育実践が行われ、そのために教師の専門性が発揮されていると見なす他はない。本当にそうなのか、なぜそれが可能なのか。
言い直そう。同じことを全員に教え込む教育学なのか、一人ひとりに合わせる教育学なのか、ここがまず日本や今日のアメリカ・イギリスとはっきり異なる。次に、フィンランド社会が教師を専門家として養成し、その専門性が十二分に発揮できる制度を作り出していることが、日本のマニュアル通りに動く教師と、行政の行う教育の品質管理制度とは大きく異なる。フィンランド教育に、OECD教育局やEU欧州委員会教育文化総局がスポットライトを当てて、歴史の寵児として扱ったことは、フィンランド教育を未来型の教育として経済界が注目したということだ。
(福田誠治「フィンランドは教師の育て方がすごい」50頁)
日本人の解釈では、正しい答えに合わせるように教え込むことが教育である。その結果、みんな行動は一致する。答えは一つ、知識も一種類しかない。学力向上とは、単一の物差しの序列を上がることに他ならない。
一つの物さしの上下が学力の違いになるというわけでだ。そして、誰もが100点をとることが理想となる。だが、これは古い学力だ。日本人の考える「生きる力」は、そのような同質性と直線的な学力観の上に立っている。
ところが西洋の場合、人間は一人ひとり違う、つまり異質なものなので、多様な人間の一致点を少しづつ増やしていき、またそれぞれのよいところを組み合わせてもっと大きな力がでるようにコミュニケーションの能力を育てようとする。これがPISA型読解力の真のねらいである。
もっている知識や技能は人それぞれ違っていて、相手や場面に合わせて使い分けていくもので、答えは一つではない。また、すぐその場で出てくるものでもない。ねばり強く解決に向かって、情報を集め、自分の考えもまた修正し、人間や自然に向かって働きかけ、解決を成し遂げなくてはならない。
読解力とは、これらの行動を系統づけ、調整し、他者や自分自身とコミュニケーションする力のことであり、そこにはメタ認知的機能も含まれているのである。(福田誠治「フィンランドは教師の育て方がすごい」214頁)
改めて考えてみると、何故、同じ地域の同じ年齢の人々が同じクラスになり、同じ授業を受け、事前に決まっている答えを覚えテストで書くというのが標準的な教育になっているのだろうか。
ここには「異質な集団」(例えば「大人」)はなく、テスト勉強をしている限り他者と協働(コラボレーション)する機会もない。
DeSeCoは、これからの人や社会が豊かになるためには、「異質性」=「多様性」をもった人々が「コラボーション」をして「イノベーション」が必要であると考え、教育目標の転換を提言したのである。
なお、地域統合を進めるヨーロッパは、従来の「国民創出」を目的とした各国の教育だけでは不十分であると考え、各国の教育目標を統一するため、「国民創出」にかわる新しい教育目標を作ろうとしている。DeSeCoはこのヨーロッパの取り組みから大きな影響を受けて作成されているが、国家の教育目標を「国民創出」とするか、国民創出に代わる「コンピテンシー」とするか、アクセンントの置き方は各国の置かれている政治状況によって異なるのだろう。
もっとも、政治状況は異なっても、求められる力に関してパラダイムシフトは生じているようである。
福田誠治氏は、明治維新時の教育観の転換を例に挙げ、子どもたちが生きていく世界は、今とは異なる明日の世界であるとして、次のように指摘する。
ちょうど、幕末から明治にかけて、日本は諸藩から国家に再編成される時に、一人前の能力観から学校で身につける能力観に変わった。
今、諸国から広域連合にあるいは地球規模に経済や政治が再編成される時に、学校で身につける学力観は固定的な学歴取得ではなく、生涯学習として開発し続ける能力観に変わりつつある。日本はそれに対応した国家戦略をもっているのか。
教育再生会議などを通じて持ち出される対策は、「愛国心」や「学力テスト」のような訓練的学力観であって、「攘夷!」「攘夷!」と叫んで鎖国を続け、武術の鍛錬に励もうとする斜陽の武士に似ていはしないか。
今の日本に、国内でしか通用しない知識や偏差値や学力テストの順位を過大視する大人の何と多いこことか。子どもたちの生きていく世界は、それとは違う明日の世界なのだ。私たちは「未来の学力」を子どもたちに用意しなくてはならない。
(福田誠治「フィンランドは教師の育て方がすごい」226頁)
reflectivenessの向上
第二のポイントは、「異なる集団の中で交流すること」が”reflectiveness”を向上させるという点である。以下みていきたい。
現在の社会が抱える様々な問題の、根本的な原因は一体何か。
この点、『社会力を育てる」(岩波新書)の著者である門脇厚司氏は、「子ども」が「一人前の大人」となるプロセス、つまり、自らが社会の一員であると自覚し、自分のためだけではなく、他者のためにも自分の力を活用し、他者と協力して物事を行うことができるような人になるプロセス(「社会化」)に異変が生じていると指摘する。
この「子ども」を「一人前の大人」とするプロセスの異変こそが、いじめ、不登校、退学、無気力、引きこもり、学卒無業者、テレビ依存、薬物依存、リストカット、自殺、売春、児童虐待など様々な問題の根本的な原因であり、
逆に、もし、このプロセスを回復させ、自分のためだけではなく他人のためにも自分の力を活用し、他者と協力して物事を行うことができる「一人前の大人」を育成することができれば、これらの問題はもとより、地球環境や貧困や社会的格差、食料問題、紛争などあらゆる問題を解決することができると。
では、何故、「子ども」を「一人前の大人」とするプロセスに異変が生じたのか。
それは、これまで「社会化」を担っていた地域のコミュニティが崩壊し、子どもが大人と直接的に交流する機会が激減したからである。
私の見方はすでに序章で述べたところであるが、日本人の社会力が衰退したのは、社会力が培われ、育てられ、強化される上で、最も重要な「現場」である他者と相互行為する機会と場と時間が極度に少なくなったことにあるといっていい。
その結果、ヒトの子が社会人として成長していく上で最も重要な「他者の取り込み」が不全となり、それゆえに自我の形成も不全となり、他者への関心や愛着が薄れることになる。そのため、他者との関わりや他者との協働、他者との相互行為など自ら避けるという性向(predisposition)が強まる悪循環が生じることになったからだと言える。
こうした悪循環をどう断ち切るか。生まれた直後からの社会力育てを果敢に進めることである。まずもって、大人が、日常生活の現場で、子どもと積極的に関わり、子どもとの応答(相互行為)と協働を意図して行うことである。もっとありていにいえば、子どもを交えた社会生活を大いに楽しむこと以外に有効な手立てはない。(門脇厚司「社会力を育てる」152頁)
明治維新以来、日本は、第一次産業(農業、漁業)、第二次産業(工業)、第三次産業(サービス業)と産業構造を変化させながら経済成長を遂げたが、それは農村部から都市部への大量の人口移動をもたらした。
この結果、農村部のコミュニティはほとんど崩壊した反面、都市部には、「隣人が誰か分からない」ということに象徴されるように、新しいコミュニティは生まれなかった。また、大家族から核家族へと変化し、、一世帯あたりの平均人数も、1960年までは平均5人だったのに対し、現在は平均3人に減少している。
現在、子育てとは親の責任であると考えられ、それが当然のことであると考えられている。しかし、実は、この考えはここ40年程度の新しい考えであり、それ以前は、子育てとは社会(コミュニティ)の共同責任であると考えられていた。
例えば、生まれた子どもには、「取り上げ親」(赤ちゃんを取り上げた産婆さん)、「乳付け親」(最初の授乳を別の母親に頼む)、「拾い親」(子育ちのよい家にいったん拾ってもらう)、「名付け親」など様々な「仮親」がいた。
また、「産飯」「三日祝」「宮参り」「食初」など、子どもの成長の節目節目には、地域の大人が集まって「同じ釜の飯を食う」機会があるなど、子育てに多くの大人が関わる仕組みとなっており、子どもは一定の年齢になると「子ども組」「子守仲間」「若者組」「娘組」など地域の集団に組み込まれ、親は子育てから離れていく。
このように、子育ては村総がかり、コミュニティ全体で取り組むものであり、決して親の単独の責任ではなかったのである(辻本雅史「教育を「江戸」から考える」156~168頁)
しかし、コミュニティが崩壊した結果、子どもが実の両親以外の大人と交流する機会が激減する。
人とのつながりと「社会化」
それでは、子どもと大人が直接交流する機会が減少すると、何故、「一人前の大人」になることが困難になるのだろうか。
この点、門脇氏は、「生きている多くの人たちとのつながりの中に身をおいてこそ、「社会がある」ということを、そして「社会の中で生きている」ことを実感できる」という。
人が「私も社会の一員である」という自覚をもつことができるのはどうしてだろうか。
私の見方を言えば、様々な人たちと好ましいつながりができており、普段から親しく付き合いつつ、自分のやるべきことをやったり、誰かのために何かやってあげたりすることで、誰かに感謝されたり便りにされたりすることから生じる自尊的な感情がおおもとにあるからである。心地よい人間関係の中にあって、そこに信用でき信頼できる誰かがいて、自分もまた誰かに認められ頼りにされ、互いに助け助けられつつ生きているとき、人は「私も社会の中にいる」と実感できるのであり、そこから「自分も社会の一員である」という自覚を募らせていくことになる。
それとは逆の場合はどうであろうか。
一日のほとんどを一人で過ごし、誰とも付き合うことがない。それゆえ頼りにできる人ができるわけでも身近にいるわけでもなく、また自分を認め自分を頼りにしてくれる人がいるわけでもない。このような場合、その人が「自分が社会の中で生きている」と実感することはまずないはずである。なぜなら、社会の実態は日々生きている人間がそこにいることであり、そこで生きている多くの人たちとのつながりの中に身をおいてこそ、「社会がある」ということを、そして「社会の中で生きている」ことを実感できるからである。
このような認識の上に立って、日本の人びと、とりわけ若い世代の現状を見るとき、悲観的になるのを禁じえない。社会の一員であるという自覚が生まれる原点ともいえる他者との緊密なつながりを自ら切断するか、つながりそのものをつくろうとしなくなっている人たちが多くなっているように思えるからである。(中略)
多様な他者と好ましい人間関係を築くことをせず、むしろ他者を貶め、攻撃する心性の持ち主が増えているとしたら、そこから「私も社会の一員である」という意識が生まれてくる可能性はきわめて低い。「私も社員の一員である」という自覚をもつことができないとしたら、公共心や道徳心が培われることはない。
公共心とは、煎じ詰めれば、社会の一員であるという意識があり、それゆえに社会のためになることを進んでする心根のことであるからである。また、道徳心とは、端的に言えば、いい人間関係を築いたその他者とのいい関係を今後とも損ねないようにしようとする他者への配慮の心であり、他者を大切にし思いやる諸々の行為のことだからである。(門脇厚司「社会力を育てる」30~32頁)
人とのつながり、様々な大人と交流する機会をもつことによって、子どもは「自分も社会の一員である」という自覚をもち、自分のためだけではなく、他者のためにも自分の力を活用しようという心根を持った人になる。
つまり、「異質な集団で交流すること」というキーコンピテンシーの育成によって、”reflectiveness”が向上するというである。
では、人とのつながりや交流がもたらす「社会化」に焦点をあわせた教育は行われているだろうか。
例えば、以下のよな取り組みがある。
- 茨城県東海村、毎週土曜日を「テレビを見ない日」にし、子どもと大人が交流する機会を作る活動。
- 長野県の幼児教育振興プログラム、社会力形成を目的とし、大人と子どもの交流を促進するプログラム。幼稚園や小中学校での交流事例などを紹介。親子でのスタンプラリーや手作り料理を家族で楽しむためのレシピの配信など。
- 山形県戸沢村、子どもを対象とし、蝶の保護、わら細工や門松作り、河川の美化、山林の伐採や炭焼き、酪農の手伝いなどを大人と一緒にする「地域の学校」づくり、子どもと大人の四泊五日の合宿、他の家のお風呂に入らせてもらう「もらい湯」など。なお、このような取り組みの結果、全国学力テストの成績が著しく向上した。
- 長野県青木村、山形県戸沢村をモデルとした活動を開始
- 京都府舞鶴市、子どもたちが、地域の課題を大人たちの協力を得ながら解決策を考える総合学習を実施。
- ラボ教育センター、英語教育を軸に大人と子どもが話し合い、演劇、泊り込みの合宿、海外でのホームステイなどを実施。
- 筑波大学大学院、学生が市民団体やNPO活動に参加し社会力を育成するカリキュラムを作成、実施。
- NPO法人ニュースタート、不登校や引きこもった若者に、食堂経営、デイサービス、託児施設などに参加してもらい、集団生活や仕事の体験を通じて、社会復帰を支援する活動(以上、門脇厚司「社会力を育てる」178~202頁)
- 東京都和田中学校杉並区立和田中学校 – Wikipediaの取り組みをモデルとした、学校教育に大人が協力する仕組みとしての、文部省の学校地域支援本部学校支援地域本部に関すること:文部科学省
- スポーツを軸とした地域のコミュニティ作りを進める文部省の総合型地域404error:文部科学省など
しかし、門脇氏は「”人と人がしっかりとつながっていること”の重要性を念頭において改善策や教育政策が構想され、議論され、考えられることがまだまだ少ない」と指摘し、次のようにいう。
くどいようであるが、本章の最後に、もう一度、社会生活を営むための社会力の重要性について述べておくことにしたい。
社会の将来について想いを巡らすときも、近い将来、社会の担い手になる子どもたちの教育について議論するときも、あるいは社会が直面している様々な問題の解決策を考えるときも、制度や法律をどうするかといったことは頭にあっても、残念ながら、”人と人がしっかりとつながっていること”の重要性を念頭において改善策や教育政策が構想され、議論され、考えられることがまだまだ少ないと思うからである。
これまで何度も述べてきたことであるが、社会をつくっているのは、私たち人間である。日々社会の中で泣き笑いしながら生きている私たち人間なのである。このことはまぎれもなく社会的な事実なのである。このことがわかれば、社会の質は社会をつくっている人間の質にかかわっていることも容易にわかるはずである。
社会が安定的に維持されているかどうかは、その中で人びとが安心して暮らしていけるかどうかで判断できることであり、社会が活力を保ちさらなる発展を遂げることができるかどうかは、そこで人々が将来に希望をもって生きているかどうかにかかっていることである。
こう考えれば、社会の現状を見る目や社会の将来を考える視点は、自ずと、人びとの営む日常的な社会生活に注がれることになるはずである。そして、社会生活の現場とも核心ともなっている人びとの交わりの”実際の場”である相互行為に注がれることになるはずである。そして、さらには、社会を考えるポイントが日々相互行為をする人びとの”人とつながる力”いかんに絞られるはずである。
こうして、今、目をこの点に凝らしてみると、現代人の人と人をつなぐ磁力といえる社会力が極度に衰弱していることに気付く。ではどうするか。私の答えは、当然ながら、「社会力を育てるしかない」ということになる。(門脇厚司「社会力を育てる」145~146頁)
柔道
以上、「異質な集団の中で交流する」というキーコンピテンシーについて、第一に、これからの人には「同質の集団」だけではなく「異質の集団」で交流する必要があること、第二に、「異質な集団の中で交流すること」によって、自分のことしか考えられない「子ども」を自分のことも相手のことも共に考えられる「大人」に変貌させること(社会化、reflectivenessの向上)の重要性についてみた。
それでは、DeSeCoがこれからの人は「異質な集団の中で交流すること」が必要であると教育目標を定義したことは、柔道のあり方にどのような影響を及ぼすだろうか。
柔道の実績
第一に、柔道は「異質な集団の中で交流する」という機会を作り出し、人々のreflectivenessを向上させてきた、特に子どもたちの「社会化」を図ってきた、という事実を改めて確認すべきだろう。
親に無理やり道場につれられてきた素行不良の子どもが、稽古をするうちに素行が良くなったということはよく聞く話である。
これは、つまり、柔道が、子どもが、その先生や他の仲間、仲間の親などと直接交流する機会を作り、その結果、「多様な大人たちとの直接的な交わり(相互行為)を通して、子どもたちの中に多くの大人が他者として取り込まれ」、「社会の一員であると意識が生まれた」ということである。
重要なポイントなので改めて確認するが、人とのつながり、様々な大人と交流する機会をもつことによって、子どもは「自分も社会の一員である」という自覚をもち、自分のためだけではなく、他者のためにも自分の力を活用しようという心根を持った「大人」に変貌する。
この「社会化」のプロセスが正常に機能するようになれば、人も社会も豊かになるが、逆にうまく機能しなければ、苦しい生を送ることになる。なぜなら、社会の一員であるという自覚の低い、つまり道徳のレベルが低い場合、嘉納の表現を借りるならば、「自己の欲するところは事ごとに他人の利益を衝突し、社会国家人類の福祉と矛盾する」からである。
道徳上の最も低い位置にあるものは、自己の欲するところは事ごとに他人の利益を衝突し、社会国家人類の福祉と矛盾する。それゆえに、道徳の高い人は、他のためになること、すなわち徳行することが、自身の満足と一致する。道徳の低い人は、もし道徳を行うとか、正しいことをしようと思えば、絶えず苦痛を感ぜざるを得ぬのである。
現代は、従来の地域コミュニティが崩壊し、また社会が「複雑化」し、「無縁社会」という言葉が流行るように、人とのつながりが希薄化しているという。
このよう状況において、柔道は、世代や性別、民族、宗教などを超えて「異質な集団の中で交流する機会」を作り出し、人々のreflectivenessを向上させてきた。このことの意義とポテンシャルがどれほどのものであるか想像がつくだろうか。
いずれにせよ、第一のポイントは、この柔道が社会において果たしてきた役割を改めて確認することである。
嘉納
さて、嘉納が万人のreflectivenessを向上させるために柔道を創ったということは前々回ふれた。
要は、自分のことだけしか考えられない「子ども」が他者のために自分の力を活用できる「大人」に変貌した(「社会化」)とは、「精力善用・自他共栄」の精神を身につけたということである。
第二のポイントは、嘉納は、「異質な集団の中で交流する機会」がreflectivenessを向上させることを認識しており、「異質な集団の中で交流する機会」を万民に提供しようとして、柔道を作り、また、オリンピックに日本を参加させ西洋スポーツの振興を図ったという点である。
嘉納は、道徳教育と体育を併用する理由について次のようにいう。
道徳教育は、単に講釈や訓戒だけでは存外力のないものである。実際の行いに結び付けて話もし、注意警告もしてこそ効能が現れやすいのである。
しかるに教育者は、概して生徒と起居を共にしているものではない。普通の教場においては、教員は時間時間に当嵌められてある各種学科の教授に忙殺されていて、教室においては一般的に教訓する機会が少ないが、運動場においてまたは道場においては、個人として生徒に接触する機会が比較的多い。そういう場合に、あらゆる手段を尽して道徳教育を施せば、存外効果のあるものである。
(嘉納・著作集3巻312頁)本稿第13回第13回 道徳は独立の課目としては教えない。 – 勇者出処 ~嘉納治五郎の柔道と教育~
嘉納は、「運動場においてまたは道場においては、個人として生徒に接触する機会が比較的多い。」から道徳教育が効果的があると考え、そのため柔道やスポーツを普及させたのである。
勝ち負けに拘泥する
これら第一、第二でみたように、柔道は、これからの人と社会が豊かになるための「異質な集団で交流する機会」を提供することができるし、そもそも原点からそのような目的をもっていた。
それでは、現在の柔道は、十分に「異質な集団で交流する機会」を提供しているだろうか。つまり、「他人といい関係を築く」「協力する。チームで働く。」「争いを処理し、解決する」ような力が身につく教育を施しているだろうか。
この点、柔道ルネッサンスは「ややもすると勝ち負けのみに拘泥しがちな昨今の柔道の在り方を憂慮し」て開始されたが、少年サッカーではあるが、永井洋一氏によると、勝敗のみを重視した結果、人を平気で蔑む子供が育てられているケースがあるという。
□
このように、監督・コーチ、あるいは両親が勝敗の結果のみを重視する考え方になり、そのために優勝劣敗の哲学を振りかざしていると、それが子供にも伝播し、子供も同じように露骨な優勝劣敗の考え方を持つようになってきます。
その結果、レギューラーに選ばれて試合で活躍している優れた能力を持った子供は、やがて、能力に恵まれない子供を見下したり、力の劣った対戦相手を平気で蔑んだり、不利な判定を下した審判を批判したりするようになります。
また、勝てる試合でミスをした仲間をなじり、「勝つためにはあの子が穴だ」などと考えたり言ったりするようにもなります。そして、「何ができるようになったか」という過程を重視することよりも、「何位に入ったか」「何回勝ったか」というように勝敗や数字に表れる結果で物事を判断するようになります。(永井洋一「スポーツは「良い子」を育てるか」65~66頁)
□
チームスポーツには他者への思いを育み、自他を協調させていく能力を伸ばすという側面があります。それは、人と人とのコミュニケーション力を醸成する能力を養い、やがて社会をつくる力となる可能性を秘めています。
ところが、かのチームの子どもたちのように、自分の力を誇示し、弱い相手を蔑むことを平気で行うように育てられたとすれば、チームスポーツを行うことが、必ずしも社会をつくる力として昇華されないということになります。
(永井洋一「スポーツは「良い子」を育てるか」166~167頁)
実態は分からないが、「勝ち負けのみに拘泥」した場合、自分の力を誇示し、弱い相手を蔑むという性向をもった子ども、つまり、「異質な集団の中で交流する力」が弱い子どもを育ててしまうおそれがある、という指摘は注意すべきだろう。
最後に
最後に、これから子どもたちは、今とは比較にならないぐらい、「異質な集団」と交流する力を身につけなければならないが、どのようにすればこのような力が身につくのだろうか。
本稿の提案は、これまで検討してきたように、次のような経験を多くの人々に、特に青少年に提供する仕組みを創ることである。
- 異なる地にある道場(国外・国内問わず)にいって、その地の先生の指導を受け、その地の仲間たちとともに稽古をすること、
- そして、可能であれば関係者宅にホームステイをさせていただき、稽古している期間、その地で生活すること、
「かわいい子には旅をさせよ」「他人の飯を食う」「同じ釜の飯を食う」、
もし、柔道がこのような「異質な集団の中で交流する」機会はより多くの人々に提供することができるのであれば、世界で最も優れた教育機関の一つになるのではないだろうか。
※本記事は、2010年8月から酒井重義(judo3.0)によってブログで連載された研究論考「勇者出処~嘉納治五郎の柔道と教育」の再掲です。

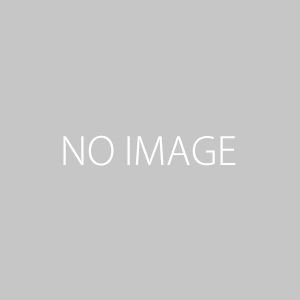
最近のコメント