前回、現代の課題とは、現代に即した通過儀礼(イニシエーション)を大人が協力して作り上げることにあるのではないか、もしこのように捉えると、柔道が歩むべき新たな道が見えてくるという点にふれた。
子どもを別人のごとく大人に変えることができた古代社会・原始社会のイニシエーション(通過儀礼・成人式)は、宗教学者エリアーデによると、概ね以下の4つの要素が含まれるという。
- 「聖所」が用意される。ここに村の男たちが集まり神話を再現する営みが行われる。
- 子どもたちを母親から引き離す。
- 子どもたちは村から隔離されたキャンプで共同生活をし、部族の宗教的伝承などを教え込まれる。
- 割礼、抜歯、入墨等のある種の手術を受け、また、徹夜や断食、ある種の食事制限など様々な制限や禁止に従う。
では、イニシエーションは、どのようなメカニズムで子どもを大人に変えることができたのだろうか。
以下、「冒険」「友情」「神話」という三つの視点からみていきたい。
「冒険」
何故、イニシエーションは子どもを「別人」の如く大人に変えることができるのか。
第1の理由は、未知の世界で出会う困難や試練を乗り越えたから、すなわち「冒険」をしたからである。以下、イニシエーションにおける冒険の特徴を4点あげる。
旅立ち
冒険の第1の特徴は、子どもは母親から引き離されることである。
「大人」になるためには母親から離れなければならない。例えば、劇的な例として、オーストラリアのムルリング族では、子どもが母親と一緒に地面に座っているとき、突然、男たちが走ってあらわれ、子どもを連れ去っていくという。
慣れ親しんだ世界を離れ、原始の森林に連れ去られた子どもは、これは自分はどうなるんだろう、という恐怖に打ち震えながら、冒険が始まったことを知るのである。
エリアーデは次のようにいう。
この祭儀の最初の部分の意味、新入者を母親から引き離すことの意味は、まったくあきらかである。われわれの考えるところでは、子供の世界との絶縁‐ときとしてまったく乱暴な断絶なのであり、この子供の世界とは、同時に母の、そして、女性の世界であり、無責任と幸福、無知と無性的な子供の状態なのである。
(エリアーデ「生と再生」28~29頁)
嘉納もまた、嘉納塾を運営し、知人の子どもを預かり起居を共にして教育を施したが、それは「親の膝下にあってはついあまやかされて自然的に困苦欠乏を味わい得ないという人々は、塾において修行する必要があると信じ」ていたからである。大人になるためには母親から離れなければならない。
異界
冒険の第2の特徴は、何処に行くか、という点に関係するものである。
文化人類学者ヴァン・ジェネップは、様々な儀礼において、(1)旧世界からの分離、(2)旧世界から新世界への移行、(3)新世界への合体という三つのプロセスが共通して存在することを見出した。
一方から他方に移る人は誰でも、しばらくの間は具体的にも、呪術‐宗教的にも、特殊の状態におかれる。すなわち彼は二つの世界の間をゆらゆらと揺れているのである。この状態こそ私が「移行」(marge)と呼ぶものであり、本書の一つの目的は、この理念的かつ具体的な移行が、ある社会的または呪術‐宗教的な状態から他への通過に伴うすべての儀式に、多かれ少なかれ明確な形態のもとに見いだされるということの証明にある。
(ヴァン・ジェネップ「通過儀礼」24頁)
そのうえで、人は、この「移行」の期間、「二つの世界の間をゆらゆらと揺れている」特殊の状態、すなわち「社会の外に位置」していることを見出した。
さて、通常の経済的、法的結びつきは、全見習い期間を通じて、大きく変化し、場合によっては全面的に断ち切られる。イニシエートされるものは、社会の外に位置し、社会は彼らに対して―特に彼らは実際に神聖で神的な性格を帯び、したがって神々がまさにそうであるように、不可触かつ危険な存在になっているのであるから―何の影響力をもたない。
(ヴァン・ジェネップ「通過儀礼」124頁)。
つまり、イニシエーションにおいて、子どもは、人の俗なる世界のルールが及ばない、神や精霊、亡霊が住まう異界に旅立つのである。日本の神話でいうところの「黄泉の国」である。
現代の人々が、神や精霊、魔物などの存在を肌で感じることは稀だろう。しかし、古代社会や原始社会には、社会の外に存在する神や精霊、亡霊や魔物の住まう世界があった。何の困難も危険もない安全な地に旅立つのではない。イニシエーションにおいて、子どもはまさしく「黄泉の国」に行き、そこから戻ってくるのである。
試練
冒険の第3の特徴は、何らかの試練を乗り越えることである。
「人は一連のひどく困難で、危険でさえある状況を克服してはじめて、自己形成をなしとげる」(エリアーデ「生と再生」256頁)というとおり、困難を乗り越えることが精神的成長を促すことは明らかだろう。イニシエーションでは人為的に子どもたちに困難な何かを提供する。
ここで着目したい点は、多くのイニシエーションでは何らかの肉体的な苦痛や困難が用意されており、「肉体的試練は精神的目標を持つ」という点である。
・・いろいろの肉体的試練にも精神的意義が含まれている。新入者は同時におとなの生活の責任をになう準備をさせられ、進んで精神生活に目覚めさせられるのである。試練や禁制にはかならず神話、ダンス、パントマイムなどを通しての教育が付随するからである。肉体的試練は精神的目標を持つ-若者を部族の文化に導き入れ、精神的価値を「自覚」させる。(エリアーデ「生と再生」41頁)。
すなわち、イニシエーションでは、歯を折る、割礼、断食、徹夜、殴打される、食物を手で食べてはならない、入墨を入れる、髪の毛を抜く、土の中に埋められる、蟻にかまれる、毒草によってむずがゆくされるなど、裸で生活するなど身体的につらい体験を伴うことが多い。すなわち、「身体」に対する刺激を通じて「精神」の発達を図ろうとするのである。
この点、教育学者の辻本雅史氏は、「身体」という「回路」を通じて、日常を超えた超越的かつ根源的な「いのち」に触れることができると古来から考えられてきたことを指摘する。
宗教的な修行は、洋の東西を問わず、あるいは宗教の種別を問わず、たいてい激しい苦行が課せられています。ほとんど生命の極限にいたるほどの激しい身体的な修行が、なぜ必要なのでしょうか。
宗教によって、その説明の論理や言い方などは違うでしょう。しかし、激しい身体訓練のうちに、言葉で語られる理論や説明では届かない、深い精神世界に潜入し悟入する確かな回路がある、そう確信されている点では、共通しているのではないでしょうか。
宗教は、ある種の超越的な世界に悟入することを目指しています。すなわち、宗教的な超越の世界は、「心で考える」いわば言語的な過程を越えて、身体を回路とすることによって、はじめて悟入できるということに違いありません。
「身体」は、実はもっとも身近な「自然」です。また身体は「いのち」の「在処」、というよりもむしろ「いのち」のはたらきそのものにほかなりません。
「いのち」は一つ一つ個体として簡潔して存在する、あるいは一つの「いのち」はその個体の「持ち物」である、といった考え方をするのは、たぶん「近代人」だけでしょう。「いのち」は、それを生みだした「大いなる自然」の一部を構成するのです。このように考える思想の方が、歴史的にはるかに普遍的だと思います。
この意味で、儒学が前提とする「天地自然」は、「大いなる自然」であり「大いなるいのち」ととらえられます。そして人の「いのち」としての身体は、「天地自然」の一部を成している存在です。
とすれば、身近な「自然」としてのこの「身体」を回路とすることによって、人は、日常を超えた超越的かつ根源的な「いのち」(生命)にふれることができる、そう考えてよいでしょう。
そのように考えれば、「いのち」の在処であるこの「身体」こそ、自分が超越的で根源的な世界につながる接点にほかならないのです。
(辻本雅史「教育を「江戸」から考える 学び・身体・メディア」145~146頁)
本論考で何度もふれてきたが、この「身体」を通じて「精神」の発達を図るという考え・手法(徳育としての体育)は、嘉納治五郎のそれと同じである。
もっとも、この考え・手法は、実は、近年まで公に語られることはなかった。「脳から見た学習」を研究した経済協力開発機構(OECD)は、2010年、次のようにいう。
比較的最近のことだが、神経科学の発達によって、精神と肉体はまったく別物であるとするデカルト主義的な従来の考え方に異論が唱えられるになった。身体的な健康や体調が精神的能力に直接的な影響を及ぼすことは確かであり、その逆もまた同じである。したがって、教育現場では、身体的能力や精神的能力に直接影響を与える環境要因に加えて、身体的能力と精神的能力の相互関係も考慮する必要がある(OECD教育研究革新センター「脳からみた学習」95頁)。
ヨガが普及しているように、身体を通じて心を整えることは多くの人に馴染んだ考え方であるが、これまで公に教育の場に取り入れられることはなかったという。身体と精神の接点にある脳の研究によってはじめて可能となってきたのである。
死と再生
冒険の第4の特徴は、子どもは冒険を通じて単線的に成長して大人になったのではなく、いったん死んで、大人として再び生まれてきた、と自他とともに認識されることである。
子どもはいったん(象徴的に)死んで、白紙になったからこそ、別人のごとき大人になることができたのである。
イニシエーション的試練の大部分は、多かれ少なかれ、復活もしくは再生を伴う儀礼的死を意味する。あらゆるイニシエーションの中心のモミュメントは、修練者の死と、その生者の仲間への復帰を象徴する儀式によってあらわされる。しかし、修練者は新しい人間として生まれかわる。つまり別の存在様式を身につける。イニシエーションでの「死」は同時に幼年時代の終焉、未知と俗的状態の終止を意味する(エリアーデ「生と再生」9頁)。
すなわち、子どもは「大人」になるためにはいったん死ななければならなかった。そして死は「大人」という新しい存在形式の始まりであった。エリアーデは、この点(死に積極的意義を見出したこと)にイニシエーションの最も重要な点があるという。
要するに、具体的な死は結局はより高い状態への過渡の儀礼に同化されるということになるのだ。加入礼的な死は、すべての精神的再生、霊魂の残存、その不死性にとっての「必要欠くべからざるもの」(sine qua non)となる。加入礼と儀典と原理が人類史上に持ってきたもっとも重要な結果のひとつは、この儀礼的死の宗教的評価が、ついに人びとをして本当の死の恐怖を打ち克たしめ、人間存在の純粋に霊的な残存の可能性に対する信仰に導いた点である。
(エリアーデ「生と再生」268頁)
ここでのポイントは、子どもは、死の恐怖を経験し、それを乗り越えることを通じて精神が発達したという点にある。
割礼や抜歯などある種の手術をする場合(神々によって実施されると聞かされている)はもちろん、既に、子どもは母親から引き離されたとき、死の恐怖で一杯になっている。少々長くなるが、エリアーデはその恐怖を次のように語る。
この祭儀の最初の部分の意味、新入者を母親から引き離すことの意味は、まったくあきらかである。われわれの考えるところでは、子供の世界との絶縁‐ときとしてまったく乱暴な断絶なのであり、この子供の世界とは、同時に母の、そして、女性の世界であり、無責任と幸福、無知と無性的な子供の状態なのである。
この絶縁は、母親にも修練者にも強い印象を与えるような方法で行われる。事実、ほとんどすべてのオーストラリアの部族の例では、母親はその息子が、おそろしい、神秘的な神、名は知らないが、その声はブル・ローラーの肝をつぶすような響きで聞くことができる神によって、殺され食べられてしまうのだと知らされる。彼女らはもちろん、神ややがて成人の形に、すなわち成人式儀礼を通過した成人として修練者を生き返らせるのだと保証されてはいる。しかしいずれにせよ、修練者は幼年者としては死に、母親たちは、子供たちがもはやイニシエーション以前の子供、つまり彼女の子供ではなくなるという不吉な予感を持つのである。少年が最後にキャンプに帰ってくるとき、母親は手でさわって、ほんとうに息子かどうかをたしかめる。あるオーストラリア部族では-他の部族もそうであるが-母親は、死者をいたむ如くに、受礼者をいたみ弔らう。
修練者にとって、その体験はさらに決定的なものである。彼らは始めて宗教的な畏敬と恐怖を感じる。なぜなら神々にとらえられ、殺されるだろうと、かねて聞かされているからである。彼らが子供だと見なされている限り、その部族の宗教生活には何の役割も果たし得ない。もし偶然に神秘的存在者に関することがらや、神話や伝説の切れはしを聞くことがあっても、それがどんなことがらなのか分からないのである。おそらく死者を見たことがあっても、それがどんなことがらなのかははっきり分からないのである。おそらく死者を見たこともあろうが、しかし死が自身に関連することがらだという意識はおこらないのである。彼らにとっては、それは外部の「ことがら」であって、他の人々、とくに老人だけにおこる神秘的事件なのである。しかし今や、突如として、その仕合わせな幼年の無意識状態から引き離される。そして死なねばならぬ、神々によって殺されることになるのだと聞かされるのだ。母親から引き離すという行為そのものが、彼らを死の予感で一杯にしてしまう―なぜなら彼らは未知のもの、しばしば覆面した人々にとらえられ、日頃なじんできた環境から遠くへ連れ去られ、地面の上へねかされ、小枝で覆われるからである。
初めて彼らは暗黒という未知の体験に直面する。それは彼らが以前に知っていた暗黒、自然現象としての夜‐夜はけっして全くの暗黒ではない、そこには星があり、月があり、火がある‐の暗黒ではなく、絶対の、おびえさせらるばかりの闇、神秘的存在者の満ちた、そして何よりもブル・ローラーの響きによって告げられる神の近づきに肝をつぶすような暗さなのだ。この暗黒、死、神々の接近という体験は、つねにこのイニシエーションを通じてくりかえされ、深められてゆく。しかし、この祭儀のまさしく最初の行事が、すでに死の体験を意味していることを強調しておく必要がある。というのは、修練者は突如として未知の世界に投げ込まれ、そこでの神々の現存が彼らにふき込まれた恐怖を通じて感じとられるからである。
母の住む世界は俗界である。修練者がいま入る世界は聖界である。この二つの世界の間には断絶があり、連続は絶たれている。俗界からある種の聖界に進むことは、死の体験を含意している。この過渡をなすものは別の生命を獲るために前の生命を絶たなければならない。ここにしめしている例では、修練者はより高い生命、聖へ参加が可能となる生命を手に入れるために、幼年時代、子供の存在の無責任性-すなわち、俗的存在-を死ななければならない。
(エリアーデ「生と再生」28~29頁)
古代社会・原始社会が提供した死と再生の機会(イニシエーション)は、近代になって失われた。しかし、人は、今でも、無意識的にイニシエーションを求めているという。例えば、深夜、バイクを暴走させる若者は何を求めているのか。
心理療法家の河合隼雄氏は、失われた「死と再生」の機会、すなわちイニシエーションを求めてのあがきなのではないと指摘するのである。
ある男性が、高校を出て浪人していたが、学業が手につかずぶらぶらしていると思っているうちに、暴走族に仲間入りしてしまった。単車を乗りまわしているその姿を見ていると、死ぬことを求めて努力しているのではないかと思えてくる。このような例ばかりではなく、青少年の犯罪や、あるいは家庭内暴力の例などに接していると、そこには常に「死」ということが誘因としてはたらいているように感じられる。
このような例をみると、そこに認められる無意識的な「死の希求」は、イニシエーションにおいて重要な「死と再生」の体験をもとめてのあがきではないかと思えてくる。もちろん、イニシエーション儀礼における「死と再生」はあくまで象徴的体験である。そのような象徴的体験をする方策も奪われてしまって、なおイニシエーションの必要性が迫ってくるとき、それは短絡的な死の希求へと走ってしまうのではないか、と思われる。当人はそんなことを意識しているわけではない。その暴発的行為が、イニシエーションを求めてのあがきと解釈されるのである。(「講座心理療法 心理療法とイニシエーション」4~5頁)。
冒険のまとめ
以上、(1)母親から引き離されること、(2)この世ではない世界(異界)に旅立つこと、(3)肉体的な負荷を通じて精神の発達を図ること、そして、(4)死の恐怖に直面しそれを乗り越えること、というイニシエーションにおける冒険の特徴にふれた。古代社会・原始社会は、大人が協力して、子どもたち全員に対し(特に男子に対し)、このように手の込んだ冒険の機会を提供していたのである。
友情
何故、イニシエーションは子どもを「別人」のごとく大人に変えることができたか。
「冒険」に続く二つ目の理由は、「友情」である。
イニシエーションの間、子どもたちは村から隔離され、一定期間共同生活を送りながら同じ釜の飯を食べ、苦楽をともにする。
文化人類学者ヴィクタール・ターナーは、通過儀礼において、「各自の存在の根源に達し、その存在の根源において深い連帯性をもち、分かち合えるなにかを見出すような、人間変革の体験」(ヴィクター・W・ターナー「儀礼の過程」192頁)があることを見出し、これを「コミュニタス」と命名した。
この点、文化人類学者の青木保氏は、コミュニタスをともにした仲間は「世間の常識では思いもおよばないくらいの慈愛で結びついている」と指摘する。
「リミナリティ」にある人間はこうした絶対服従を生きるが、それと同時に、「全き平等」がそこでの生活の原理になっている。この状態におかれた人びとが、独特の仲間意識を発生させるとは前にも述べたが、この意識は姉妹兄弟の間や同級生や同期入社といった人間どうしの間に見られる仲間意識とは、まったく異なるものである。この状態にある人びとが創りだすのは完全な共同社会であって、いかなる点においても、階層序列的な関係はない。みんな同じである。この共同性は、地位、年齢、性、宗派、親族組織の中の位置、などの「差異性」を超越するものであって、そこでは「個は全に、全は個に」という原理が貫かれている。
この平等原理も、基本的にタイのピク・ナワカの間に見られるものといってよいのだが、これも民族誌が数多い事例を提供してくれる。ザンビアのウンデブ人の成人式の場合、割礼を受けるためにそれまで「隠されていた」少年たちに、彼らの母親が「差し入れる」食物はすべて平等に全員に分けあたえられる。首長の息子であろうが貧乏小作人の子供であろうが、万事平等にとりあつかわれる。少年たちの隠される場所は村の外の繁みの中であるが、そこでは長老がすべて食事を平等に分けてあたえるものである。
ンデンブ社会では、成人するためにこうした隠遁所に隠されて修練を受ける少年たちの間には深い友情が育まれるといわれている。夜になると、小屋のたき火のまわりで四、五人ずつかたまって眠る。彼らの間で発達した特別の紐帯は、儀礼がおわってもからも崩れることなく続き、生涯にわたって無くなることはない。この友情関係は、ウブワブムとよばれるが、それは授乳を意味し、互いに世間の常識では思いもおよばないくらいの慈愛で結びついている。利害関係や法的規制によって妨げられることのない純粋な人間関係が、そこに生まれるのである。これはタイのピク・ナワカの「同期」修行者どうしの間でも多かれ少なかれ見られる現象である。
「リミナリティ」は、このように一般社会ではまず見られることのない、あるいは単に理想として考えられるにしかすぎない、特別な平等と友愛の関係を生み出し、発達させる。長老の権威への「絶対服従」といい、仲間どうしの間の純粋な「平等主義」といい、いずれも「日常的現実」の世界にあっては、理想であり観念でしかないと通常考えられているようなことが、ここでは実現する。日常生活において曖昧にしかありえないことに、はっきりとした輪郭をあたえて実現させる。それが、どっちつかづの「境界」において出現するのである。これは「真実である」というフレームによるメタ・コミュニケーションとして。(青木保「儀礼の象徴性」288~290頁)
では、このコミュニタスという全人格的な人間関係、そこで生まれる強い慈愛に満ちた友情、こういったものが人間の、子どもの精神的発達にどのような影響を及ぼすのだろうか。
この点、心理学者のエリクソンは、思春期・青年期の課題は、アイデンティティ、すなわち、「自分は何者であるのか。何者でありたいのか。どんなふうに生きていくのか。」にあるとした。
この課題に対応できない場合、時として、人はいったい自分は何者なのか、何をしたいのかが分からなくなり、対人関係がうまくいかなくなったり、無気力になったり、非社会的、反社会的行為にはしってしまう。
では、人はどのようにしてアイデンティティを形成するのだろうか。
友情によって、である。
児童心理学者の佐々木正美氏は、価値観を共有する友人との交流によってアイデンティティが形成される旨を指摘する。
自分はどういう人間に選ばれたか、自分はどういう友達を選んだかで、自分はどういう人間かということにもなります。そして、自分がやりたいことやなりたいものは、他者との関係で決まるのです。この時期に大切な他者は、先生や尊敬する人も重要になりますが、それ以上に大切なのは、話が合う、気持ちが合う友達が、数はかぎられてもかならず必要です。価値観を共有することができる友達です。そういう友達と親密に交流することが、アイデンティティを形成し、支えてくれるのです。友達の自分に対する評価や感想の蓄積が、自己像(アイデンティティ)の基盤になるのです。
(佐々木正美「完 子供へのまなざし」121頁)
人間というのは、だれもがみんな、生まれたら「私」になれるというわけではありません。「私」というものをしっかりもつためには、他者のイメージを自分のなかにたくさん取りこまなければ、「私」というものはできないのです。自分を知る人は、他者をよく知っている人のことです。他者がいるから自分があるということです。ですから、他者と深いまじわりをすることなしに、「私」というものはできないということです。
他者の深いまじわりをするには、自分のなかに取りこみたくなるようなイメージの人に、たくさん出会ってこなくてはいけないわけです。いいかえれば、自分のなかに他者のイメージを取りこむためには、自分にとって好ましい人のイメージからしか取りこめない、ということもわかってきました。
だから自分を苦しめるような人とか、不幸にするような人にいくら出会っても、自分というものはできあがってこないわけです。自分に喜びを与えてくれる人、自分を幸福にしてくれる人、自分にはできないことをしてくれる人に出会うと、その人のイメージを自分のなかに取りこむわけです。
そうすると、人の善意というものを信じることができる。人を信じることができるようになった子どもがはじめて、たくさんの人のイメージを安心して取り入れるようになり、自分を大切にしてくれる人を信じることができるのです。そして、人に大切にされる自分を信じることができる。このようにして「私」という自己概念ができ、自信ができてくるのです。
自分に自信ができてくると、他者への信頼もでき、人を好きになってきて、人と安心してまじわれるようになってくるのです。このようにして自分の世界がどんどん広がって、「私」というものが、どんどんしっかりできてくるわけです。(佐々木正美「完子どもへのまなざし」123~124頁)
人は、価値観を共有する友人の目に映る自分の姿を受け入れることを通じて、自分とは何者か、何をすべきか、を知る。古代社会・原始社会の大人は、子どもたちに対し、日常の世界からは想像もつかない、慈愛に満ちた生涯にわたる友情を育む機会を創りだした。子どもは、この友情によって精神的発達を遂げ、大人になることができたのである。(続く)
*1:なお、イニシエーションにおける身体的苦痛は主に男性を対象としている。女性の場合、初潮があったとき村から隔離され、そこで性についてや部族の習慣などが教えられ、大人の女性として村に帰還するいうケースが多い。これは、女子の場合、自然に身体が大人に変化し、この身体の変化に伴って精神が変わるからであり、逆にいうと、男子にはそのような自然の身体的変化がないからこそ、手の込んだ儀式が必要となってくるという。
※本記事は、2010年8月から酒井重義(judo3.0)によってブログで連載された研究論考「勇者出処~嘉納治五郎の柔道と教育」の再掲です。
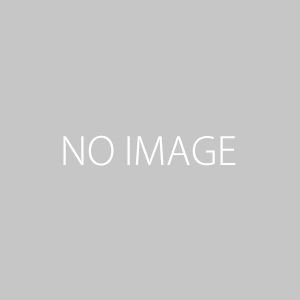
最近のコメント