人の苦しみや争いの根源は、精神的に未成熟な「子ども」を、社会の一員として成熟した「大人」に変えるシステムの機能不全にある。こういった視点からみると、古代・原始社会は、イニシエーションという優れたシステムを持っていた。
そこで前回まで、一体どのようにして、古代・原始社会のイニシエーションは「子ども」を「大人」に変えたのか、という点について、「冒険」「友情」「神話」という切り口からみた。
それでは、何故、共同体はイニシエーションを運営することができたのであろうか。
確かに、未成熟な大人を養う余裕がない古代・原始社会では、子どもが「大人」に変貌できるか否かは、その共同体の存続にかかわる重要の課題である。しかし、重要という理由だけで大人が総出で関与するイベントを長年開催できるとは限らない。このイベントを運営する大人には、どのようなインセンティブがあったのだろうか。
それは、イニシエーションは「神話」を「再現」する「祭り」という形式をとっていた点にあると思われるが、以下みていきたい。
神話の再現
前回、神話(物語)には「つながり」や「意味」をもたらす機能があり、子どもはイニシエーションにおいて開示された神話によって、身体と精神、外界と内界、意識と無意識などが結び付けられ、成熟した大人になることができたことにふれた。ポイントは、この神話の伝え方にある。
神話は、学校の教室で先生が生徒に情報を提供するような形で伝えられたのではない。
大人は、神話上の環境を再現する建造物を作り、神話上の人物を演じ、参加した子どもが神話を擬似的に体験できるよう様々な仕掛けを用意することによって伝えた。いわば体験型アトラクションである。
例えば、神話的祖先が、冒険の過程で、怪物と対峙し殺され、そして一部身体が欠損した状態で再生し、世界を作り上げたのであれば、イニシエーションにおいて、目隠しをされた状態であたかも怪物が登場したかのような音が流れたり、参加者の歯が一本砕かれたりする。
前回、イニシエーションが子どもを大人に変える過程を「冒険」「友情」「神話」という切り口でみたが、つまり、イニシエーションとは、子どもに対し、神話的祖先がたどった足跡を追体験する「冒険」を用意し、神話的祖先と類似の人物を作り上げようとする試みであったといえる。
古代心性を理解するために加入礼に関心を持つのは、とりわけて真の人間-精神的人間―は与えられるものでも自然的な経過の結果でもないことをはっきりさせている点である。人々は神々が啓示し、神話に保存されている手本にしたがい、老師によって「形成される」のである。
(エリアーデ「生と再生」269頁)
ポイントは、神話を再現して子どもを大人に変えようとするイベントは、共同体そのものを再生する「祭り」でもあったという点にある。この神話を再生するというイベントは、大人にとっても、自らが神々の世界とつながり、生活が新たに再生される「祭り」であった。だからこそ、大人が総出で関与してイニシエーションが行われたのである。
成人式儀礼は神々や神話的祖先によってその基がひらかれたのであるから、その儀式が執行されるときはいつでもその原初のときに再統合されるのである。これはたんにオーストラリア人にとってのみならず全未開世界にとってそうなのである。なぜなら、ここにしめされているのは、古代宗教の基本的観念であり-神によって基礎を置いた儀礼をくりかえすことは、それが始めて執行されたその始原のときの再現を意味する-、それは聖なる、始めのときの完全性にあずかることになるのである。この儀礼は神話を現在のものとする。神話が始めのとき、「ブガリ時代」(bugari times)に語っていることがらを、儀礼は、ここに、そして今おこったかのように再現し、示すのである。西キンバレー部族の一つのバード(Bad)族が子供に成人式を施すために準備するとき、古老たちは森のなかに隠れてガンボール(ganbor)樹をさがすのである。それは「祖先時代に-ジャマール(Djamar)-この部族の最高神-がこの木の下で休息したことがある」からである。先頭を行く妖術医は「この木を見つけ出す役割を負うている」。それが見つかると、人々はこの木をとりまき歌をうたったあと、火打石製の刀で伐り倒す。神話の木はかくて現然化する。
イニシエーションの間それぞれつづいて行われるすべてのみぶりや手術は、たんに規範的モデルの反復-すなわち、神話時代に、この儀式の創立者によって執行されたみぶりと手術なのである。この事実こそ、彼らを聖なるものとし、これを周期的にくりかえすことでその社会の全宗教生活が再生されるのである。
(エリアーデ「生と再生」24頁)
宗教的祝祭は太初の出来事、すなわち神々や半神を主人公とする「聖なる歴史」の再現である。「聖なる歴史」は神話のなかで語られる。祝祭の参加者はしたがって、神々や半神的存在と同時代の者となる。彼らは神々の現在と活動とによって浄められた原初の時に生きる。聖なる暦は時間を、起源の時、「強力」にして「純粋な」時と一致させることにより、周期的にこれを再生させる。祝祭の宗教的体験、すなわち聖なるものへの参与は、人間がくり返し神々の現在に生きることを可能にする。モーゼ以前のすべての宗教において、神話が重大な意味をもつ根拠はここにある。神話は神々の振舞い(gesta)を物語、これらの振舞いがすべての人間活動の手本である。宗教的人間は、その神々を模倣する度合いに応じて、起源の時、神話の時代に生きる。換言すれば、彼は俗なる持続から脱出して、「不動の」時、「永遠」への接続を見出すのである。(中略)
宗教的人間にとって、同一の神話的事件の再現は、あらゆる希望の中で最大のものである。なぜなら再現するたびごとに、またその生存を変じて神的典型に同化する可能性が得られるからである。原始ならびに古代社会の宗教的人間にとっては、模範的行為を永久に反復し、神々によって浄められた同一の神話的起源の時に永久に遭遇することは、何ら悲観的人生観の条件とはならない。反対にこの神聖にして真実なるものの根源へ「永久に回帰」することのみが、彼らの目から見れば、人間の存在を無と死から救うのである。
(エリアーデ「聖と俗-宗教的なるものの本質について」98~99頁)
脱神話化した現代から古代人の心性を想像することが難しい点があるが、現代でも「祭り」は未だ各地で行われている。何故大勢の大人が祭りの運営に関わるのか、という点から見た場合、古代の祭りと同様、祭りという非日常の時空間が参加者の日常生活を活性化するからといえるだろう。
文化人類学者ターナーが「構造的な活動は、それに関わる人たちが定期的にコムニタスという再生力のある深淵に沈潜することなしには、たちまちに、無味乾燥となり機械的になってしまう(「儀礼の過程」193頁)」と指摘するとおり、日常の生活は、何らかの「祭り」(コムニタス)があるからこそ活力を保つことができる。
近代以前とそれ以後の違い
以上、「祭り(=神話の再現)」という形式であったからこそ、多くの大人が、子供を大人に変えるイベントに参画することができたという点をみた。
それでは、何故、古代のイニシエーションは消失したのか。また、古代のイニシエーションを現代にそのまま再現することはできないのか。以下、2点ほど近代以前と以後の大きな違いにふれたい。
神話という「迷信」からの解放
1点目は、「個人の自由」や「社会の進歩」という点に関係する。
前回もふれたが、古代社会は、神話という特定の世界観を共同体の皆が共有していた。皆が共有する世界に「入れてもらう」ためにイニシエーションが機能したのであるが、心理療法家の河合隼雄氏は、ここに「進歩」という概念が存在しないことを指摘する。
イニシエーション儀礼が成立するためには、その社会が完全な伝承社会であることを必要としている。古代社会においては、極言すれば、すべてのことは原初のとき(かのとき)に起こったのであり、この社会(世界)は既に出来あがったものとして存在し、後から生まれてきたものは、その世界へ「入れてもらう」ことが最も大切なことなのである。したがって、子どもが大人になるためには、その世界へと入る儀式としての、イニシエーション儀礼が決定的な意味をもつのである。つまり、そこには「進歩」という概念が存在せず、この世はできあがった世界、閉ざされた世界としてあり、子どもが大人になるときにそこに入れてもらうことになるのである。
(河合隼雄「大人になることの難しさ」62~63頁)
近代は、集団ではなく個人にこそ価値があり、物事は科学的に合理的に考えるべきであるという思想に基づき、多くの神話を否定した。この結果、イニシエーションが失われ、子どもが大人になることが難しい社会になった。
しかし、その反面、近代は、神話を「迷信」であると否定したことから、個々の共同体に囚われた人々を解放し、個人の自由や社会の進歩を図ることができたという側面がある。例えば、「母なる大地」という神話のもとで、当時、個人が土地を私的に所有し自由に処分できるなど考えられないだろう。
したがって、当然ながら、近代以前と以後は、社会の主要な価値観が異なる点に目を向けなければならない。古代のイニシエーションが古代社会の人々の社会適応(子どもから大人への精神的発達)を支援したとおり、現代に求められるイニシエーションもまた現代社会の人々の社会適応を支援するものである。
もし、現代の社会的規範に反する神話に基づきイニシーションを行ったならば、それは単なる反社会的な、または非社会的な行為を助長する洗脳イベントとなってしまう(その典型は、地下鉄サリン事件などのいわゆるオウム真理教事件だろう。オウム真理教では「イニシエーション」が行われていたという)。
グローバル化した世界
2点目は、人の住む世界がグローバル化した点に関連する。
「個人の自由」と「社会の進歩」は、典型的には、人の移動できる距離、取引ができる範囲の大小に表れる。古代社の社会で、移動距離や取引範囲は小さかったが、近代以降、著しく拡大し、世界各地の人々が相互に依存するようになった。
この点、「世界を読む力」を著した寺島実郎氏は、わずか百数十年前の世界と今の世界の違いを次のようにいう。
いま、あなたが百数十年前の日本にタイムスリップしたと想像してみてほしい。場所は東北のとある山村地帯。
あなたはそこで暮らすひとりの若い女性に着目する。毎朝、鶏の鳴く前から起きだして、川に、山に、畑に休む間もなく働く女性‐「とんでもない労働量だな」と、あなたは、きっと目をむくだろう。けれど、何ヶ月何年と観察するうちに、ひとつの疑問が脳裏に浮かんでくる。
「この人、この村から出たことがあるのだろうか?」
小さな村のなかで一日が完結する生活。それが、ほんの百数十年前までの、平均的な日本人の暮らし方であった。特に女性の場合は、せいぜい隣村に嫁ぐことが人生最大の大移動。当時の多くの日本人にとって、「世界」は、歩いて日帰りできるだけの範囲ー半径二〇キロメートルほどの広がりしかなかったのである。
翻って、百数十年後の現代日本を眺めてみる。いまでは、ひとりの人間が日帰りできる範囲は、自動車を使えば半径二〇〇キロメートル、飛行機を使えば一〇〇〇キロメートルを優に越えている。「アジア日帰り圏」などという言葉が出るぐらい、わたしたちの行動できる「世界」は、ぐんぐん広がっているように見える。
激変したのは交通手段ばかりではない。現代は、ヒト・モノ・カネ・技術・情報が、ボーダーレスに、つまり「境界なし」で交流する時代である。ラジオからテレビ、そしてインターネットへと、様々なメディアが登場・普及し、情報環境が劇的に変化して、わたしたちが認識できる「世界」は限りなく広がったように見える。「わたしは、いながらにして世界のすべてを知ることができる」と強弁する人がいたとしても不思議ではないだろう。
だが、私たちの「世界を知る力」は、単純に、交通手段や情報環境の発達と正比例して向上するものだろうか。残念ながら、答えは「否」である。
(寺島実郎「世界を知る力」3~5頁)
海外の信用不安が当然のように自国の信用不安に影響を及ぼすものとして報道されるように、人の住む世界は大きく広がった。
そして、人の住む世界は「地球」という一つの共同体である、このことを自覚させるものが二酸化炭素の排出による地球温暖化などの環境問題である。もはや一地域や一国で解決できる問題ではない。
例えば、このほか環境問題には以下のようなものがある(ジャレド・ダイアモンド「文明崩壊 滅亡と存続の命運を分けるもの (下)」310~324頁)。
- 森林・湿地・珊瑚礁などの自然の棲息環境の破壊(森林破壊は過去の文明が崩壊した主要な原因)
- 海産資源など野生の食糧源の減少(約20億人が海産資源に依存)、
- 人類の存続を無償で支えていた生物の多様性の喪失(土壌の再生に寄与していたミミズがいなくなる)、
- 急速な土壌の浸食(農地が減少していく)、
- 石油等の化石燃料の枯渇、
- 水資源の減少、
- 農薬・冷却材・洗浄剤・プラスチック等にも含まれる毒性化学物(不妊の増加や大気汚染)、
- 外来種がもたらす生態系の破壊
いずれも一地域一国でのみ対応することが難しいものであるが、このほか、地球という一つの共同体に属していることを自覚せざるを得ない典型例として、人類全体で消費する地球資源の量が増大し、限界に近づいていることから、これに対する制限をかけなければいけないという問題がある。
すなわち、アメリカ、西ヨーロッパ、日本の住民は、平均して、第三世界の住民の32倍の資源を消費していると言われるとおり、先進国の豊かな生活は地球上の資源を大量に消費することによって成立している。この先進国のような豊かな暮らしを、今、第三世界は願い、生活水準の向上を図っている。この結果、人類全体で消費する地球資源の量が増大しているわけだが、地球には、巨大な人口を有する第三世界の生活水準を先進国なみにするほどの資源を持っていない。
この点、「文明崩壊」を著したジャレド・ダイアモンドは次のようにいう。
近い将来、第三世界のすべての人々が、現在の先進国の水準には到達し得ないことを、また先進国がみずから現在の水準を手放そうとはしないことを悟ったとしたら、どういう事態が出来するだろう?世の中は妥協という土台の上に立った苦渋の選択に充ち満ちているが、これはわたしたちが迫られている最も過酷な妥協だと言っていい。
(ジャレド・ダイアモンド「文明崩壊 滅亡と存続の命運を分けるもの (下)」324頁)
これらの環境問題に象徴されるように、もはやどんな出来事も「対岸の火事」として眺めることができないほど相互依存し、地球という一つの共同体に住んでいるという前提から考えざるを得なくなった。人の住む世界は、半径十数キロという規模から地球という規模に著しく拡大したのである。
神話の機能不全
さて、問題は、いまなお力がある神話の多くが、この世界が拡大したという事実に対応していない点にある。その典型は、各地で多発する宗教上の違いに起因する紛争である。
神話は多くの場合、自分が属する集団が「正しい」「優れている」と考え、その他の集団は「間違っている」「劣っている」と考える傾向にある。共通の敵を設定し、又はスケープゴードをつくることによって集団内の利害調整が行われるということは現在でもよくあることである。
この点、ある神話を共有する集団と他の集団が物理的に離れていて、お互いにあまり影響を及ぼさないという社会であれば、その神話がどんな内容であれ紛争が起きるということも少なかった。
しかし、今や、世界は、様々な集団が入れ混じった一つの地球共同体である。このなかである集団が優れ、ある集団が劣っているという内容を含む神話は当然ながら人々の争いを生み出す。つまり、小さい地域内で他の集団と頻繁に混じり合うことがないゆえに機能した昔の神話が、広範囲な地域で他の集団と頻繁にまじりあう現代で機能不全を起こしているのである。
したがって、近代以前と近代以後では、人の住む世界が違うということを自覚しなければならない。宗教に限らず、人種、性別、民族など何らかの属性に着目し、ある集団が正しく、そして優れており、他の集団は間違っていて、劣っている、という内容を含む神話は、平穏な世の中を生み出すことができない。人の住む世界が「地球」にまで拡大した以上、地球上の生きとし生けるものすべてと調和を保つことができるような神話が必要なのである。
八方ふさがり
以上、近代以前と近代以後の違いを見た。
近代以前とそれ以後の社会の価値観は大きく異なり、ゆえに古代の多くのイニシエーションは失われた。そして、いま力ある神話の多くも争いの種になっている。それでは、いっそのこと神話やイニシエーションなど一切不要なのではないか、といっても、人はイニシエーションを必要としている。
この点、心理療法家の河合隼雄氏は、現代の子どもの「問題行動」の原因を次のようにいう。
制度としてのイニシエーションは、近代社会において消滅した。しかし、人間の内的体験としてのイニシエーションの必要性は無くなったわけではない。ここに現代人の生き方の問題が生じてくる。子どもが大人になるということは実に大変なことだ。だからこそ、古代においては社会をあげてそれに取り組み、それぞれの社会や集団が、それにふさわしいイニシエーションの儀礼や制度を確立してきた。それを無くしてしまったのだから、個人に対する負担は大変重くなった。言うなれば、各人はそれぞれのイニシエーションを自前で自作自演しなくてはならなくなった。
しかしながら、現代人の多くは近代の流れのなかにそのまま生きていて、イニシエーションの制度のみならず、イニシエーションそのものも「迷信」として否定してしまっている。意識的に拒否しても、人間存在に根ざすイニシエーションの必要性は、無意識の働きとして生じてくる。そのとき両者の乖離があまりに著しいと、いわゆる「問題行動」としてそれが露呈されてくる。かくて、心理療法家のもとに訪れてくる、あるいは連れて来られる人たちの多くが、イニシエーションの成就を目指しての仕事をわれわれと共にすることになる。
(「講座 心理療法1 心理療法とイニシエーション」9~10頁)
多くの神話は失われ、いまある神話の多くも機能せず、かといって、既に個々人が自作自演しているとおり、イニシエーションを不要とすることもできない。それでは、このにっちもさっちもいかない状況をどうしたらいいのだろうか。
実はここに、神話学者ジョーゼフ・キャンベルに導かれ、忽然と柔道が現れてくるのである。
※本記事は、2010年8月から酒井重義(judo3.0)によってブログで連載された研究論考「勇者出処~嘉納治五郎の柔道と教育」の再掲です。
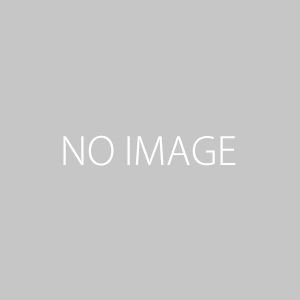
最近のコメント