前回までイニシエーションについて考察し、(1)イニシエーションの中核にあるものは神話であること、(2)近代は、神話の喪失によってイニシエーションが失われ、子供から大人への成長が困難になった時代であること、そして、(3)もし現代に即した新しい神話があれば、現代に即した新しいイニシエーションを構築できることにふれた。
神話がキーになるわけであるが、神話学者ジョーゼフ・キャンベルは次のようにいう。
ある人間が他の多くの人のお手本になったとき、その人は神話化の過程に入っているわけです。
(ジョーゼフ・キャンベル「神話の力」文庫版65頁)
イニシエーションとしての柔道
世界200カ国以上の国々に普及した柔道、その創始者である嘉納治五郎は多くの人々のお手本になっているが、実は、嘉納治五郎の物語は「神話」なのではないだろうか。
実は、ひとたび嘉納治五郎の物語が「神話」として捉えると、柔道のこれからの姿が明瞭に現れてくる。それは、柔道とは、嘉納治五郎の物語を再現する通過儀礼、「イニシエーション」であるという認識であり、「イニシエーション」として機能する柔道である。
本稿は、柔道の新しい仕組みとして、世界200カ国以上のネットワークを活用し、青少年が異国の道場にいって、異国の人々と寝食を共にして稽古をする機会を提案しているが、実は、これは世界が共有する新しい「イニシエーション」の提案にほかならない。
以下、(1)これまで何度かふれたが、改めて、「神話」は人間の発達とどのような関係があるのか?、(2)何故、嘉納治五郎の物語が神話なのか?、(3)イニシエーションとしての柔道とは何か?という三つの点から敷衍していきたい。
神話は人間の発達とどのような関係にあるか?
嘉納治五郎は、ヨーロッパを訪問した際、精神科医のグスタフ・ユングを訪ねたようであるが(ユングは留守だった)、人間の発達と神話の関係を考察したのがこのユングである。以下分かりやすくするため、大幅に単純化してユングの考えをみていきたい。
「発達」しなければ神経症になる。
まず、ユングは、精神科医として多くの患者の診察をしたが、そこで直面したことは、人は精神が適切に「発達」しなければ、何らかのトラブルを抱え込むことになるということであった。
人生のさまざまな問題に対して不適切なあるいは間違った回答を出して甘んじているとき、人は神経症になることを、私はこれまでに何度となく見てきた。彼らは、地位、結婚、名声、外面的な成功、金を追い求めるが、自分が求めているものを手に入れたときですら、不幸で、神経症的なままである。そうした人々はふつう、あまりに狭い精神的な枠のなかに閉じこめられている。彼らの生活はじゅうぶんな意味をもっていない。もし彼らがもっと広い人格へと発達することができれば、神経症は一般に解消する。それゆえ、発達という観念は、私にとってはつねに何よりも重要だったのである。(アンソニー・スティーブンス・鈴木晶訳「ユング」185頁)
その時々に適切な「発達」がなければ何らかの精神的トラブルを抱えることになる。このことは、例えば、心理学者エリクソンは、年齢に応じた発達課題として次のように指摘している(エリクソンの発達課題心理学COCOROの法則: エリクソンの心理社会的発達理論)。
- 0~2歳で、自分自身や周囲の人を基本的に信頼する「基本的信頼」。これが身に付かないと自他を信頼できなくなる。
- 2~3歳で、自分の衝動をコントロールする「自律性」。これが身に付かないと自分は自分を恥じるようになる。
- 3~6歳で、自分の周りに積極的に働きかける「自発性」。これが身に付かないと自発的に活動することはよくないことだと思ってしまう。
- 6~13歳で、周りから期待される行動を自発的・継続的に行う「勤勉性」、これが身に付かないと自分は劣っていると感じるようになる。
- 13~22才で、自分とは何者かを定めて自らの道を歩む「アイデンティティ」。これが身に付かないと自分が何をしたいのか分からなくなる。
- 22~40歳で、異性などと親密な関係を築いていく「 親密性」、これが身に付かないと孤独になる。
- 40~65歳で、次の世代を育成する「世代性」。これが身に付かないと停滞する。
- 65歳~で、死を前にしてこれまでの経験を統合していく「統合性」。これが身に付かないと絶望する。
このように、ユングは、人は発達しなければ精神障害など何らかのトラブルを抱えるという事実に直面し、どうしたら人は発達できるのか、そもそも何故人は発達ができるのか、という考察に向かった。
人は、何故、「発達」できるのか。
その結果、ユングは、まず前提として、人は、自分では自覚できないが、生まれながらにして精神の発達を促すプログラム(「集合的無意識」「元型」)を持っているという結論に至る。
たとえ近代化が大きく人の生活を変えたとはいえ、人間が抱える精神的な課題は古来からほとんど変わらない。例えば、小さいときは家族に依存しなければならない、あるとき独立しなければならない、集団の中で働かなければならない、家族をもち子供を育てなければならない、大切な人をいつかは喪わなければならない、いずれ老いて病気になり死んでいかなければならない、などであるが、これらの課題は人類誕生のときから同じであり、古今東西の人間が乗り越えてきた課題である。
ユングは、人には(自分では気づかないが)これらの課題に対応するプログラムをもって生まれてきており、適切なタイミングでこのプログラムが起動するからこそ、人は「発達」することができる、逆に、何らかの理由でこのプログラムがうまく起動しないとき、精神的なトラブルを抱えるようになると捉えたのである。
患者はこんなふうに考えるようにと教えられる -症状は存在全体の不均衡から生じたのであり、その不均衡は、元型の意図が実現されなかったことの結果である、と。治療とは元型の欲求不満を正し、一面性を捨てて、人格全体のなかで対立し合っている力どうしの間に新たな均衡をもたらすための方法を見つける助けをすることである。それをなしとげるには、自分の意識的な状況だけに係わっていたのでは充分でない。大事なのは無意識の状況を知ることである。そのためには夢分析と転移分析が欠かせない。(アンソニー・スティーブンス・鈴木晶訳「ユング」189~190頁)
このように、ユングは、人の心の中には「無意識」という領域があり、ここに精神発達のプログラムが内包されていると捉えたのであるが、それでは、どうしたらこのプログラムを適切に作動させることができるのだろうか。なにしろ、このプログラムは自分では分からない「無意識」の中にあり、コントロールできないのである。
「物語」や「イメージ」の効用
ユングは、このプログラムを作動するキーは、「物語」や「イメージ」であると考えた。
臨床的診断は重要である。医師に、ある一定の方向をあたえるからである。だが、診断は患者の役に立たない。もっとも重要なのは物語である。物語だけが人間的背景と人間的苦しみを明るみに出すのであり、その点からのみ、医師は治療に取りかかることができるのである。
(アンソニー・スティーブンス・鈴木晶訳「ユング」180頁)
具体例として、死というものの存在に脅かされた6歳の子どもが、物語やイメージをもつことで乗り越えた事例をみていきたい。
ある母親がその6歳の男の子のことについて相談に来られた。その男の子が最近になって、死のことについて質問するので困るというのが、その相談の内容だった。家庭は幸福で病人はいないし、最近、知人で死んだ人もいなかった。しかし、その坊やは、自分が大きくなったときのことを考えているうちに、もし自分が80歳くらいになると、お父さんやお母さんはどうなるかを考え始めたらしい。このことは必然的に、死の問題につながり、人間は死ぬとどうなるのかということにもなった。
・・この坊やは、「お母さん、また悲しい話をしようか」といって、母親のところに来て、死について自分の考えたことを話したそうである。あるときは、両親も死ななければならないときがくると話して、泣きながら、「悲しい話だけど、話さないといられない」ともいった。これらを、母親は泣きながら聞き、話し合ったそうである。
しかし、解決はほどなく、この男の子の内部からやって来た。あるとき、この坊やは生き生きと目を輝かして、「お母さん、とうとうよいことを思いついた」とやって来た。「僕が死んでも、もう一度お母さんのお腹の中に入って、また生まれてくるとよい」と、この子は話し、これで、すっかり死の話をしなくなったという。(河合隼雄「ユング心理学入門」201~202頁)
この子どもは、死におびえるようになり、一種の精神的な危機を迎えたわけであるが、「僕が死んでも、お母さんのお腹の中に入って、また生まれてくる」という物語やイメージを得ることによって乗り越えることができた。単純にいうと、この物語やイメージを得たことによって、無意識下のプログラムが作動し「発達」したのである。
「物語」や「イメージ」の特徴
この無意識下のプログラムを発動する物語やイメージには、二つの特徴がある(河合隼雄「ユング心理学入門」104~129頁)。
一つは、本人にとって生き生きしたものである、という点にある。
ユングは「理念の特徴が、その明確さ(clarity)にあるとすれば、原始心像の特徴はその生命力(vitality)にある(河合隼雄「ユング心理学入門」112頁)」というとおり、「お母さんのお腹の中に入って、また生まれてくる」という物語・イメージは、本人にとって、心に響く、自ら体験したかのような生き生きとしたものであった。
単で頭で、知識で理解しても、通常、人の行動は変わらない。生き生きとした、心に響く物語・イメージであったからこそ、考え方や行動の変容が生じたのである。
もう一つは、その物語やイメージにとって重要なことは無意識下にあるプログラム作動のキーと機能する点にあり、キーとして機能するか否かはその物語の論理性、客観性、現実性と関係がない、という点である。
つまり、現実的に考えれば、既に生まれた人間がお母さんのお腹の中に入ることは不可能である。しかし、このような現実的にあり得ないフィクションによって、無意識下にあるプログラムが発動し、この子どもは「発達」した。
いい方を変えると、この物語やイメージは、言葉では表現できない、そして理解できない何か神秘的なものを、他の方法ではもう表現できないというぐらい、最良に表現したものなのであって(「象徴・symbol」)、子どもは、この表現を得ることで神秘的なものに近づくことができたからこそ、その神秘的なエネルギーを授かり成長することができたのである(「象徴」を得ることで精神内に生じた対立や矛盾の「再統合」が生じた)。
以前も引用したが、小説家の小川洋子は、ユング派の心理療法家である河合隼雄との対談で、物語の効用について次のように表現している。
いくら自然科学が発達して、人間の死について論理的な説明ができるようになったとしても、私の死、私の親しい人の死、について何の解決にもならない。「なぜ死んだのか」と問われ、「出血多量です」と答えても無意味なのである。その恐怖や悲しみを受け入れられるために、物語が必要になってくる。死に続く生、無の中の有を思い描くこと、つまり物語ることによってようやく、死の存在と折り合いをつけられる。物語を持つことによって初めて人間は、身体と精神、外界と内界、意識と無意識を結びつけ、自分を一つに統合できる。
人間は表層の悩みによって、深層世界に落ち込んでいる悩みを感じないようにして生きている。表面的な部分は理性によって強化できるが、内面の深いところにある混沌は論理的な言葉では表現できない。それを表出させ、表層の意識とつなげて心を一つの全体とし、更に他人ともつながっていく、そのために必要なのが物語である。物語に託せば、言葉にできない混沌を言葉にする、という不条理が可能になる。
生きるとは、自分にふさわしい、自分の物語を作り上げてゆくことにほかならない。こうした意味合いの解釈に触れた時、私は初めて、書くことの意味が何の無理もなくスムーズに心の中心へと染み込んでゆくのを感じました。(小川洋子・河合隼雄「生きるとは、自分の物語をつくること」125~127頁)
夢
このようにユングは、人は、vitalityやsymbolを有する物語やイメージが「発達」にとってポイントになることを発見し、この物語・イメージに働きかけることによって、精神的にトラブルを抱えた人々の「発達」をサポートしようと考えた。その具体的な方法が「夢」である。
人は何故「夢」をみるのだろうか?
ユングは、夢とはvitality やsymbolを有する物語やイメージであるが、人は、夢をみることによって無意識下のプログラムを作動させ、精神の発達を図っていると捉えたのである。したがって、ユング派の心理療法家は、クライアントと夢についてよく話し合う。クライアントと夢について語りながら、無意識下のプログラムが適切に発動するよう導いていくのである。
患者と私はいっしょになって、私たちすべてのなかにいる、二百万年前から生きている人間に話しかけるのだ。結局のところ、私たちの抱える困難な問題の大半は、本能、つまり私たちのなかに蓄積されていながら、昔から忘れられたままになっている知恵との接点を失ってしまったことから生じるのだ。では、一体どこに行けば、私たちのなかに住んでいるこの老人と会えるのだろうか。それは夢のなかである。(アンソニー・スティーブンス・鈴木晶訳「ユング」116頁)
神話
それでは、「神話」は人間の発達とどのような関係にあるのだろうか。
ユングは、患者の夢に介入して治療を重ねる中で、夢と「神話」、精神病患者の幻覚(無意識の表れ)と「神話」が類似していることに気がつく。つまり、単なる「迷信」であると考えられた「神話」が、実は、夢と同じように、無意識下のプログラムを発動させる、vitalityやsymbolを有する物語やイメージであったことに気づくのである。
心像と象徴の心理療法における気づいた重要性に気づいたユングは、古い時代に見出され、以後死んだままになっていた宗教の儀式や象徴の意義を研究し、これらに新しい息吹を吹きこむと同時に、各個人の心のなかから生じる象徴の意義を認め、その研究にも専念してきたということができる。(河合隼雄「ユング心理学入門」128頁)
こうしてユングは、神話とは人間の無意識に働きかけて人間の発達を促すために存在している、という神話に対する新しい見方をもたした。現実的にはあり得ないような出来事を語る神話は、実は、「物理的な功業というよりは心理的な功業を表現」しているのであり、無意識下のプログラムを発動させ人の発達を図るために存在していたのである。
悲劇から喜劇にいたる暗部に道筋にたちはだかる特別の危難やからくりをあきらかにするのが神話本来の、そしてまたお伽噺の役目である。それゆえ物語中に描かれている挿話は絵空事であり「現実ばなれ」している。この種の挿話は、物理的な功業というよりは心理的な功業を表現している。たとえ伝説がある実在した歴史上の人物を素材にしている場合ですら、勝利の事跡は真にせまる形姿でなく夢のような形姿でもって描きだされる。
それというのも、その物語の強調点はかくかくしかじかの功業がこの世で成しとげられたというところに置かれていないからである。そうではなく、かくかくしかじかの功業がこの世でなりとげられるに先立ってそれとは別の「心理的レベルでの」もっとも重要で本源的なかくかくしかじかの事柄が、だれもが夢のなかで訪れて馴染みのものとなっている迷宮の内部で成しとげられねばならぬと告げている点にこそ、そうした物語の要諦があるからだ。(ジョーゼフ・キャンベル「千の顔をもつ英雄」(上)44頁)
英雄神話
それでは、世界には多種多様の神話があるが、どのような神話が人の「発達」を促すのだろうか。
家族に依存して育った子供が、あるとき依存を脱して「大人」になることは、古今東西すべての人間の発達課題であったが、この発達課題を扱った神話が、「英雄神話」「英雄の旅」(hero’s journey)である。そして、イニシエーションは英雄の旅の再現イベントであり、子供に対し、この英雄神話を身体で体験する機会を提供して、無意識下のプログラムを作動させ発達を促していたのである。
少年期と思春期における男児の元型的課題は、世界のいたるところに見い出される英雄神話に象徴的に表現されている。英雄神話は、英雄がいかにして家を出て、さまざまな試練をいかに乗り越えていくかを物語る。試練の最たるものが、竜や海の怪物との戦いである。英雄の勝利は、一国の王座につくとか、美しい姫をめとるといった、「簡単には手に入らない宝」によって報いられる。現実においても同じである。人生の冒険へと足を踏みだすためには、家や両親や兄弟姉妹との絆をみずから断って、(ほとんどすべての伝統的社会が課す)イニシエーションの試練を生き抜き、世界のなかに自分自身の場所(王国)を勝ち取らなければならない、それをすべて達成し、妻をめとるためには、いまだ彼の無意識のなかで働いている母親コンプレックスの力に打ち勝たなくてはならない(これが竜との闘いの意味である)。
結局のところ、これは二度目の誕生であり、心的なへその緒が最終的に切断される(竜や怪物と戦う英雄は、しばしばその竜や怪獣の腹に呑み込まれ、まるで自分は帝王切開手術をやるように、その腹を切り裂いて出てくる。その結果、母親の息子としては「死」んで、姫や王国を手に入れるにふさわしい男として「生まれ変わる」のである)。思春期における男性のイニシエーション儀式は、この必然的な移行を容易にする。
(中略)
われわれの文化にはもはやイニシエーション儀式はないが、性別にかかわりにあく、いまだにわれわれすべての内にはイニシエーションに対する元型的欲求が存在している。このことは、分析を受けている患者の夢から推測できる。思春期、婚約、結婚、子どもの誕生、離婚や別居、親や配偶者の死など、人生の危機的な時期に直面すると、患者の夢にはイニシエーションにまつわる象徴がふんだんにあらわれてくるようになる。人生の新たな段階に到達するためには、イニシエーションの象徴を経験しなければならないらしい。社会がそれを提供できないならば、<自己>がそれらの象徴を生み出して、この欠点を埋め合わせなければならないのである。(アンソニー・スティーブンス・鈴木晶訳「ユング」106~108頁)
一応のまとめ
以上、「神話」は人間の発達とどのような関係があるのか?という点をみた。
人はすべて無意識下に自らの発達を促すプログラムを持っており、神話によってこのプログラムを発動させ「発達」を図っていたのである。そして、数ある神話の中でも、子供が依存から脱して大人になる課題をサポートしてきたのが英雄神話であり、近代以前の社会は、子供に対し、英雄神話を体験(イニシエーション)させ、子供から大人への「発達」を促していた。
それでは次の問いにいこう。では、何故、嘉納治五郎の物語は、この無意識下のプログラムを発動する「英雄神話」に当たるのだろうか。
※本記事は、2010年8月から酒井重義(judo3.0)によってブログで連載された研究論考「勇者出処~嘉納治五郎の柔道と教育」の再掲です。
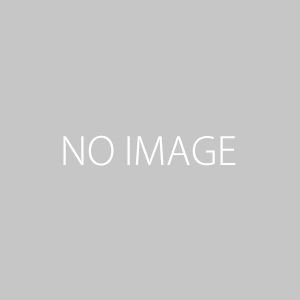
最近のコメント