※本記事は、2010年8月から酒井重義(judo3.0)によってブログで連載された研究論考「勇者出処~嘉納治五郎の柔道と教育」の再掲となります(以降の連載も同様)。
このブログでは、これから何回かかけて、柔道を創った嘉納治五郎師範(以下敬称略します。)を辿りながら、これからの柔道と教育について一つの試案を提示してみたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
テーマ
本稿は教育としての柔道について検討することにあるが、問題の所在を明らかにしておきたい。
『スポーツは「良い子」を育てるか』の著者である永井洋一氏は、少年サッカーについてであるが、勝敗のみを重視した結果、人を平気で蔑むような子供が育てられているケースを紹介し、チームスポーツの有する教育効果が発揮されていないと指摘している。
このように、監督・コーチ、あるいは両親が勝敗の結果のみを重視する考え方になり、そのために優勝劣敗の哲学を振りかざしていると、それが子供にも伝播し、子供も同じように露骨な優勝劣敗の考え方を持つようになってきます。
その結果、レギューラーに選ばれて試合で活躍している優れた能力を持った子供は、やがて、能力に恵まれない子供を見下したり、力の劣った対戦相手を平気で蔑んだり、不利な判定を下した審判を批判したりするようになります。
また、勝てる試合でミスをした仲間をなじり、「勝つためにはあの子が穴だ」などと考えたり言ったりするようにもなります。そして、「何ができるようになったか」という過程を重視することよりも、「何位に入ったか」「何回勝ったか」というように勝敗や数字に表れる結果で物事を判断するようになります。(65~66頁)
チームスポーツには他者への思いを育み、自他を協調させていく能力を伸ばすという側面があります。それは、人と人とのコミュニケーション力を醸成する能力を養い、やがて社会をつくる力となる可能性を秘めています。ところが、かのチームの子どもたちのように、自分の力を誇示し、弱い相手を蔑むことを平気で行うように育てられたとすれば、チームスポーツを行うことが、必ずしも社会をつくる力として昇華されないということになります(166~167頁)。
同様に、『子供にスポーツをさせるな』の著者である小林信也氏は、ジュニアゴルフにおけるスコア改ざんの例をあげ、「スポーツに打ち込めば必ず人間的な成長がある。」という前提に疑問を投げかけている。
熱心な親たちは、大会のときなどクラブハウスで待っていて、自分の子どもたちのスコアが悪いとき厳しく叱るんです。子どもたちの中には、親に怒られるのが嫌で、あるいは親をガッカリさせたくないばかりに、スコアを改ざんしてしまう選手が残念ながらいるんです。林の中に打ち込んだときなど、周りに誰もいなければボールをそっと動かす子どももいる。これが深刻な問題なのです(58頁)
ゴルフだけでなくスポーツの原点は、「自分との戦い」にある。ところが昨今のスポーツは他人との勝負、大会の順位や成績に注目が集まって大切な原点が軽視されている。親に怒られるのが嫌でスコアをごまかす子供がいる。それが日本のジュニア・ゴルフの現実なのだ。それでも「スポーツに打ち込めば必ず人間的な成長がある」という前提を、子どもにスポーツをさせる根拠にしてよいのだろうか(60頁)
いずれもスポーツが教育として機能しない点を指摘しているが、柔道にもこのような問題意識があり、平成13年、講道館及び全日本柔道連盟は「柔道ルネッサンス」を立ち上げた。
柔道がこのように普及してきた理由は、競技としての魅力だけでなく、創始者嘉納治五郎師範の位置づけられた柔道修行の究竟の目的である「己の完成」「世の補益」という教育面が、世界の人々に受け入れられたことに拠るものと思われます。
師範は競技としての柔道を積極的に奨励する一方、人間の道としての理想を掲げ、修行を通してその理想の実現を図れ、と生涯を懸けて説かれました。
講道館・全日本柔道連盟は、競技としての柔道の発展に努力を傾けることは勿論、ここに改めて師範の理想に思いを致し、ややもすると勝ち負けのみに拘泥しがちな昨今の柔道の在り方を憂慮し、’師範の理想とした人間教育’を目指して、合同プロジェクト「柔道ルネッサンス」を立ち上げます。
本稿は、柔道ルネッサンスと同様、
柔道は本来「人間教育」を目的として創られたにも関わらず、「昨今の柔道」は「勝ち負けのみに拘泥しがち」であり、「人間教育」として十分な効果をあげていないのではないか。
というように問題を認識し、
柔道が「人間教育」として十分な効果をあげるためにはどうしたらいいか。
という点を検討する。
解決の糸口
それでは、柔道が人間教育として機能するようにするためには、どのような考え方や問題のとらえ方をしたらいいのだろうか。
解決の糸口は、1991年に出版された、ピーター・F・ドラッカーの著書『非営利組織の経営』における、次の、ドラッカーと米国の公教育の改革を主導したアルバート・シャンカーの会話にあるように思われる。
◆ピータードラッカー:アルバート、あなたは教室での効果を向上させ、教師と学校に成果への責任をもたせ、現場の教師を中心とした学校をつくるための改革運動の先頭に立ってきました。あなたは、学校の成果をどう定義しますか。
◆アルバート・シャンカー:学校の成果を定義するには、「どのような人間をつくろうとしているのか」を考えることです。たいていの教師は、テストの成績とか、大学進学適性試験(SAT)の成績といった具体に、きわめて限定的にとらえています。しかし、本来、教育の成果というものは、三つの面で現れてくるものです。一つは、もちろん知識です。二つ目は、能動的な市民として社会に入っていき、経済活動で成果をあげる能力です。そして、三つ目は、人間としての成長と、社会の文化的生活への参加です。残念ながら、私たちは、まだ、こうした教育の成果を測定できそうだという段階にすら大して近づいていません。
◆ドラッカー:確かに、成果を測定するための目に見える知的な技術を持たない限り、基盤を欠いているというべきでしょう。何をもって成果とするかを定義するに当たっても、優先順位というものを定めなければならないでしょうね(165頁)。
ドラッカーは真っ先に「あなたは、学校の成果をどう定義しますか。」と聞いたが、何故、そのような質問をしたのだろうか。単純にいうと次のとおりである(と思う)。
- 組織は「成果」を出すために存在している。
- だから何が「成果」であるか定義しなければならない。
- 「成果」がうまく定義できないと「成果」がでない。
本稿では、このドラッカーの考えを参考にして、もし柔道が人間教育として十分な成果を出せていないとしたら、その大きな原因の一つとして「成果」の定義がうまくいっていないからではないか、と考えている。すなわち、「どのような人間をつくろうとしているのか。」が不明確な点に問題がある、と。
そこで、次回以降、「柔道はどのような人間をつくろうとしているのか。」すなわち「嘉納治五郎は、どのような人間をつくろうとしていたのか。」という点をみていきたい。
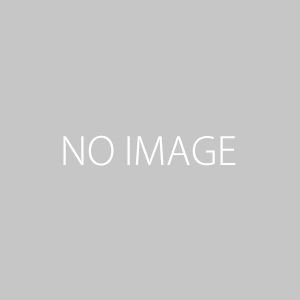
最近のコメント